
 その12へ
その12へ
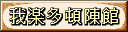
 webmaster@snap-tck.com
Copyleft (C) 2000 SNAP(Sugimoto Norio Art Production)
webmaster@snap-tck.com
Copyleft (C) 2000 SNAP(Sugimoto Norio Art Production)
平城京遷都1300年事業として平城宮跡が観光用に整備され、朱雀門と大極殿が再建されました。 それらの建物を見ると、奈良時代の権力者達がいかに”唐かぶれ(^^;)”していたかわかります。 何しろ唐の都と政治形態を真似しただけでなく、天皇の名前を初めとして貴族の名前、役所の名前、官位の名前を唐風の漢字名にし、国の公文書まで漢文にしてしまったのです。
今で言えばこれらは、総理大臣の名前を「president Naoty Kan」にし、厚生労働省を「FDA」にし、国の公文書を英語にしたようなものです。 ”西洋かぶれ”の明治政府や、社内公用語を英語にした楽天も、さすがにこれには負けるでしょう。 (^^;)
そのせいで現在でも国の公文書は漢文調の文章であり、漢文調の文章を”格調が高い”と感じるような刷り込みが民衆の心に残っています。 現代では英語交じりの文章を”先進的”と感じ、英語ができる人をインテリと考え、欧米に留学した人が高い地位に付く風潮があります。 それと同様に奈良時代は漢文調の文章を”先進的”と感じ、中国語ができる人をインテリと考え、中国に留学した人が高い位に付く風潮がありました。
「ナラ」の語源は「なだらかな土地」または「平らな土地」で、それに「奈良」という万葉仮名を当てたというのが通説になっています。 「平城京」という言葉も「平らな土地の城」という意味なので、この説には信憑性があります。
しかし、これ以外にも色々と面白い説があります。 例えば、朝鮮語で国を意味する「ナラ」が語源だという説があります。 高句麗語、満州語、そして古代日本語で土地のことを「ナ」と言いました。 例えば、土地の持ち主のことを「名主(ナヌシ)」と言うのはその名残です。 この「ナ」という言葉が国を意味する「ナラ」の語源であり、それが「奈良」の語源だという説です。
しかし「ナラ」という言葉は16世紀頃の朝鮮半島で普及した言葉のようで、古代朝鮮語で国のことを「ナラ」と読んでいた証拠は現在のところ存在しません。
また前漢が朝鮮半島に設置した「楽浪郡(nakrang、古代朝鮮漢字音でナラと発音する)」、後の高句麗の「平壌(ヘイジョウ)」を真似て、「奈良→平城京」にしたという説もあります。 この説には、7世紀頃に作られたキトラ古墳(奈良県明日香村)の天井に描かれた星宿図が、紀元前1世紀頃の楽浪郡付近で観測した天体図に相当することが最近の研究でわかり、当時の日本と楽浪郡との密接な関係が示唆されたという傍証があります。
ただし楽浪郡が高句麗によって併合されたのは313年であり、平壌と命名されて首都になったのは427年です。 この頃は、日本の古墳時代から飛鳥時代に相当します。 したがって、もし楽浪郡→平壌を真似たのなら、最初に本格的な都ができた飛鳥地方や橿原市付近を「ナラ」と命名し、藤原京を「平城京」と命名した方が理にかなっています。
平城京の前の都である藤原京(日本書紀では都の名称が「新益京(あらましのみやこ)」で、宮の名称が「藤原宮」とされている)は平城京や平安京よりも規模が大きく、内容も遜色がない古代日本の最初にして最大の都でした。 古代日本で最初にできた本格的な国や都ではなく、後になって遷都された土地を「ナラ」と命名し、都を「平城京」と命名したというのは納得がいきません。
我々は歴史を後ろ向きに眺めて、便宜上、飛鳥時代とか奈良時代という名称で呼んでいます。 しかし当時の人々は、当然、自分達の時代を”奈良時代”とは呼んでいなかったはずです。 (^^;)
しかも奈良時代の都は、平城京→恭仁宮→紫香楽宮→難波京→平城京→長岡京と何度も遷都を繰り返しています。 このため当時の人々にとって平城京は多くの都の一つにすぎず、特別なものではなかったと思います。 こういったことを考えると、奈良を「国(ナラ)」と名づけたとか、「楽浪郡→平壌」を真似たという説は説得力を欠きます。
そもそも奈良地方は古くは「添(そほり)」と呼ばれていて、その後、奈良と呼ばれるようになったのですが、その時期は都が遷都されるよりも前だったようです。
日本書紀の崇神天皇紀に、
「則ち精兵を率ゐて、進みて那羅山(ならやま)に登りて軍いくさす。 時に官軍屯聚して、草木をならす。因りて其の山を號して、那羅山と曰ふ」
という奈良の地名説話があります。 日本書紀が編集されたのは奈良時代であり、これは天皇支配を正当化するための”勝者の歴史書”、つまり時の権力者に都合の良いように捏造された歴史書ですから、内容をまるまる信用するわけにはいきません。 特に勝者の歴史書による地名説話というのは、元から存在した地名に、勝者の神話や歴史を後から無理にこじつけたものが多く、この崇神天皇紀もその類のものだと思います。
ただ、このような地名説話を作ったということは、平城京ができる以前から奈良地方が「ナラ」と呼ばれていた傍証だと思います。 当時の”唐かぶれ”の権力者にとって、先進国である唐や高句麗のものを真似るのは決して隠すべきことではなく、むしろ積極的に誇るべきことでした。 事実、藤原京も平城京も、唐の都・長安を真似たことを堂々と誇っています。
したがって、もし古代朝鮮の国(ナラ)や前漢の楽浪郡→平壌を真似て「ナラ」と命名したのだとしたら、わざわざ崇神天皇紀のような地名説話は作らず、そのことを堂々と主張したと思います。
何しろ現代の日本でも、欧米のものを真似ることは決して隠すべきことではなく、”アメリカ流○○”とか”本場フランス仕込の○○”といった形容詞で誇らしげに喧伝していますもんね。 (^_-)
古墳時代から奈良時代にかけては、中国大陸や朝鮮半島の言葉に影響を受けて日本語が大きく変貌した時代です。 このためこの時代にできた日本語には、当時の東アジア全域の歴史的関係と言語と文化に関する幅広い知識を総動員しなければ、正確に解釈することができない言葉が沢山あります。
例えば「大和(ヤマト)」は、そんな言葉のひとつです。 この言葉は、古墳時代から奈良時代にかけて、日本と中国の関係から「倭(ワ)→大倭(ヤマト)→大和(ヤマト)」と変化しました。
まず最初に中国の権力者が、「矮小な国」という意味で勝手に「倭(ワ)」と名付けました。 しかし国家としての自覚が芽生えた大和朝廷は、それに「大いなる」という意味の冠詞を付けて「大倭」とし、さらに忌字の倭を佳字の和に変えて「大和」とし、それを古来からの呼び名である「ヤマト」と無理矢理読ませました。
これは、明治政府が自らの国を「大日本帝国」と呼んだことを連想させます。 いつの時代でも、日本の権力者の考えることは変わらないようです。 (^^;)
それから「服部」と書いて「ハットリ」と読むのは、衣服を作る職能集団である「機織部(ハタオリベ)」に「服部」という漢字を当て字したものが、いつの間にか「ベ」が脱落して「ハットリ」と読むようになったからです。
「大和」も「服部」も、日本古来のヤマト言葉に外来語である漢字を当て字したものであり、漢字の訓読みと似た発想の言葉と言えるでしょう。
後に西洋からアルファベット系の表音文字を使った外来語が入ってくると、今度は外来語に漢字を当て字するようになります。 例えば煙草(タバコ、ポルトガル語のtabaco)、硝子(ガラス、オランダ語のglas)、缶(カン、オランダ語のkan/英語のcan)などがそれです。
面白いものとしては、もはや死語になってしまった「半ドン」という言葉があります。 「半ドン」は「半分ドンタク」の略で、オランダ語で日曜日または休日を意味する「zondag(ゾンターク)」が「ドンタク」となまり、週休二日制が普及する以前は土曜日が午後は休みだったため、このように呼ばれていました。 ちなみに、有名な「博多ドンタク」のドンタクも同じ語源です。 (^_-)
「大和」を「ヤマト」と読むのと同様に、奈良の春日大社の「春日」を「カスガ」と読むのも歴史的な由来があります。 春日(ハルヒ)は本来は霞(カスミ)にかかる枕詞で、春霞のことでした。 それがやがて春日大社がある土地の地名にも使われるようになり、「春日(ハルヒ)の霞処(カスガミ、霞がかかる処)」とか「春日の神住所(カスガ、神の住む処)」と呼ばれるようになり、ついには「春日」だけで「カスガ」と読むようになったと言われています。
これと同様に、「飛鳥(アスカ)」も本来は「飛ぶ鳥の明日香(アスカ)」というように地名の枕詞だったものが、いつの間にか「飛鳥」だけで「アスカ」と読むようになったと言われています。 そして「あすか」の語源は「安宿(アスク)」または「ア(接頭語)+洲処(スカ、砂地)」であり、「空を飛ぶ臆病な鳥でも安心して羽根を休めることができる土地」とか、「海や川によって生じた砂地」という意味だと言われています。
このような枕詞は謎の多い言葉で、語源不明のものが沢山あります。 そして枕詞の起源についても、諺に由来するとか、和歌の序詞に由来するとか、土地を褒めたたえる詞章に由来するとか、古代朝鮮語に由来するとか、様々な説があります。
僕は、枕詞は愛称やキャッチフレーズのようなものであり、その由来はひとつではなく、これらの説のどれもが部分的に正しいのではないかと思っています。 例えば”ファイティング”原田(我ながら古いねぇ〜(^^;))とか、”ゴッドハンド”大山倍達とか、”ゴン”中山とか、”プリンセス”メグとか、”杜の都”仙台とか、”日本のデンマーク”安城とか、”なでしこ”ジャパンといった、本名の前に置く愛称またはキャッチフレーズのようなものであり、その中で歌に流用されたものが後世に伝わったのではないかと思うのです。
こういった愛称やキャッチフレーズの由来は様々であり、インパクトを与えると同時に外国にもアピールするように外来語を使ったり、流行語を使ったりすることがしばしばあります。 それと同様に枕詞も当時の外来語つまり古代朝鮮語または古代中国語や、当時の流行語を使用したものが多かったと思います。 このため時代の流れの中で死語になり、その由来や意味が忘れ去られてしまって語源不明になったものが多いのではないでしょうか。
ちなみに奈良にかかる枕詞は「青丹よし(アヲニヨシ)」ですが、この枕詞の語源についても、奈良が顔料の青丹(あおに)の産地だったという記録があるからとか、奈良の都は青と朱色(丹)で彩られた建物が沢山あって美いからとか、諸説あります。 しかしどの説もいまいち説得力に欠け、現在のところは語源不明といった感じです。 (^^;)
飛鳥時代や奈良時代は、建物や政治形態だけでなく風俗習慣まで唐のものを取り入れようとしました。 例えば、礼の作法として唐式の「揖礼(ゆうれい)」という作法を取り入れました。 これは立ったまま両手を前で組んで頭を下げ、組んだ両手を胸または頭の高さまで上げる立礼で、中国の歴史ドラマなどでよく見かけます。
古代日本の礼は平伏叩頭(へいふくこうとう)つまり土下座か、ひざまずいて頭を垂れる姿勢でした。 相手よりも身を低くして頭を下げ、無防備な体勢を取るのは服従の姿勢であり、多くの動物に共通する本能的なボディランゲージです。 そのため土下座やひざまずいて頭を垂れる姿勢は、どんな民族にも共通する服従や礼の姿勢になっています。 古代中国でも平伏叩頭が正式な礼であり、揖礼は略式の礼とされていました。
古代日本には揖礼のような立礼の習慣はありませんでしたが、唐の風俗習慣を積極的に取り入れ始めた飛鳥時代から、貴族階級では揖礼が行われるようになります。 しかし庶民は相変わらず土下座を行っていたため、業を煮やした天武天皇が682年に「土下座を禁止して立礼に統一せよ」というお節介な勅命(^^;)を下します。
それによって立礼が普及しますが、庶民の間では両手を前で組まない単なる立礼つまりお辞儀に変化するとともに、土下座も根強く残りました。 その証拠に天武天皇の勅令から1300年以上経った現在でも、普段はふんぞり返って威張っている(これは多くの動物に共通する威嚇の姿勢です(^_-))代議士が、選挙になるとやたらと土下座をするようになります。 (^^;)
明治時代になると、やはり建物や政治形態だけでなく風俗習慣まで西洋のものを取り入れようとし、挨拶の作法として握手やハグ(抱擁)を取り入れようとしました。 しかし立礼と違って、握手やハグは現在に至るまで普及していません。 これは日本の風土と密接な関係があります。
日本は高温多湿で汗を多量にかくため、人と人が体を接することを敬遠し、相手との間に微妙な距離を置くことを礼儀にしてきました。 それは人と人が過剰にスキンシップすることを、湿気を表現する時と同じように「ベタベタする(~~;)」と表現することからもわかります。
また古代の日本人は血液や汗を介して病気が感染したり、人と接触することによって病気が感染することを知っていたので、無闇に人と接触することを嫌いました。 それは人の血液が付着したり、病気の人に触れたりすることを「穢れる」と呼んで忌み嫌っていたことからもわかります。
そんなわけで日本ではスキンシップがあまり発達せず、握手やハグという習慣は普及しませんでした。 また感染を防ぐために各自がそれぞれ専用の食器を使い、それぞれ独自に料理を盛り付ける食事作法が伝統になっていて、大皿から料理を取り分けたり、みんなで食器を共有する唐や西洋式の食事作法も普及しませんでした。
そもそも風俗習慣は風土と密接に関係しています。 それを無視して風土が異なる外国の風俗習慣をそのまま真似るのは、どだい無理というものです。 そのことは、クソ暑くて湿気が多い日本の真夏に、クーラーのない蒸し暑い部屋で握手やハグをしてみればすぐに納得できます。 (^^;)
奈良時代に使われていた万葉仮名では、同じi、e、oという母音を持つ音が甲類と乙類の2つのグループに分けられ、2種類の漢字ではっきりと区別して表記されています。 このような特殊な仮名遣いを「上代(奈良時代頃)特殊仮名遣い」といい、上代日本語(奈良時代およびそれ以前に使用されていた日本語)を研究するための重要な資料になっています。
当館の「日本語の起源」に書いたように、現在は「上代日本語には8種類の母音があった」という8母音説がほぼ定説になっていて、僕も以前はこの説を信じていました。 しかし「日本語の起源」に対して、韓国の研究者と共同で古代朝鮮語と上代日本語の関係を研究されている研究者の方から、8母音説に反対する説を紹介していただき、今ではそちらの説の方を信じています。 (^^;)
それは「上代特殊仮名遣いとは、古代朝鮮からの渡来人が上代日本語の条件異音を聞き分けて書き分けていたものであり、上代日本語には基本的に5つの母音しかなかった」という条件異音説です。
条件異音とは、前後の音環境によって同じ音が異なる音声として表れる現象のことです。 例えば日本語の「ン」の発音にはいくつかの種類があり、後に続く子音によってきちんと言い分けられています。
日本語を母国語とする人はこれらの条件異音を無意識のうちに言い分け、同じ音として認識するため、同じ表音文字「ン」で表記します。 ところが英語圏などではこれらの条件異音は別々の音として認識されるため、別々の表音文字で表記されます。
それと同様に、上代日本語の3つの母音i、e、oには条件異音があり、日本語を母国語とする人はそれらを区別していなかったが、母音が多い古代朝鮮語を母国語とする朝鮮渡来人は、それらの条件異音を聞き分けることができたため別々の万葉仮名で表記した、というのが条件異音説です。
実は、8母音説には大きな難点があります。それは3つの母音が消滅するまでの期間が短すぎるという点です。 平安時代初期に作られた表音文字のカタカナとひらがな、そして日本語の音韻表に相当する50音図には5つの母音しかありません。 したがって万葉仮名が使用されていた奈良時代から、わずか50年ほどで3つの母音が消滅してしまったことになります。 これは、母音の消失期間としては言語学の常識では考えられないほど短い期間だということです。
しかし条件異音説にしたがえば、万葉仮名は条件異音を聞き分けることができた朝鮮渡来人が発明して使用したものであり、カタカナとひらがなは条件異音を同じ音として認識していた日本人が発明して使用したものであるということになり、この難点は解消されます。 そして万葉仮名が朝鮮渡来人によって発明され、記述されたのなら、万葉仮名で書かれた文章の中に古代朝鮮語と思われる言葉があり、後世の日本人がそれらを解読できないことも納得できます。
また万葉仮名は古代朝鮮の表記法である「吏読(イドウ)」を参考にして作られたという説がありますが、万葉仮名を発明したのが朝鮮渡来人だったとすれば、この説は当然のことと納得できます。 吏読は、名詞などの実質的部分は主に漢語を用い、助詞などの文法的部分は万葉仮名と同じように漢字の音だけを借りて古代朝鮮語を表す表記法で、文法的部分は小さな漢字で表すのが普通でした。
実は、これとほとんど同じ表記法が上代日本にもありました。 それは天皇の宣命や神社の祝詞などを表記するための、「宣命書(せんめいがき)」と呼ばれる表記法です。 宣命書は、例えば、
といった具合に、実質的部分は漢語を用い、文法的部分は万葉仮名を用いて小さな文字で表記します。 この宣命書の万葉仮名をカタカナに変えたものが後の漢字仮名交じり文であり、平安時代以後、日本語の基本的な表記法になっていきます。
吏読は3世紀頃に始まって7世紀頃に確立し、19世紀末まで用いられていました。 つまり表記法が確立するまでに400年近くかかっていることになります。 それに対して万葉仮名は7世紀頃に始まり、8世紀の奈良時代には既に確立しています。 この異常に短い確立までの期間は、既に確立していた母国の吏読を参考にして、朝鮮渡来人が万葉仮名を発明したと考えれば納得がいきます。
そもそも日本に漢字を伝えたのは古代中国や古代朝鮮からの渡来人であり、漢字伝来の初期には、漢字の読み書きができたのはほとんど渡来人に限られていました。 そして吏読による朝鮮語表記法の知識のある朝鮮渡来人にとって、言語の構造が朝鮮語とよく似ており、しかも音韻体系がより単純な日本語を漢字で表記するために万葉仮名を発明するのは、容易でかつ自然なことだったでしょう。
つまり万葉仮名は朝鮮渡来人が吏読を参考にして編み出した表記法であり、平安時代初期になって、ようやく日本人がカタカナとひらがなを発明して自らの言葉を表記する方法を編み出したというわけです。
西洋の文化が大量に入ってきた明治時代にも、万葉仮名とカタカナ・ひらがなの関係と似たことが起きています。 1867年にイギリス人のジェームス・カーティス・ヘボンは、日本語を表記するためにヘボン式ローマ字を発明しました。 そしてその後、日本人が考案した日本式ローマ字が1937年に訓令式ローマ字として公認され、さらに1954年に少し改変して改めて訓令式として公認されました(現在でも、日本の標準として公認されているローマ字表記法は訓令式です)。
ヘボン式ローマ字では「シ」をshi、「チ」をchi、「ツ」をtsu、「フ」をfu、「ジ」をjiと表記します。 しかし訓令式ローマ字では、これらはsi、ti、tu、hu、ziと表記します。 shi、chi、tsu、fu、jiはそれぞれsi、ti、tu、hu、ziの条件異音であり、日本語よりも音韻体系が複雑な英語を母国語とするヘボンは、これらの条件異音を聞き分けて表記したのです。 それに対してこれらの条件異音を区別できない(または区別する必要のない)日本人は、より単純で首尾一貫した形式の表記法を用いたわけです。
いわばヘボン式ローマ字が万葉仮名に相当し、訓令式ローマ字がカタカナやひらがなに相当するといえるでしょう。
ある言語の表記体系を外国人が自国の文字を用いて作ることは、よくあることです。 その際、その言語を母国語とする人は区別していない発音を、外国人が聞き分けて別々の表音文字で書き分けるという現象がしばしば起こります。 例えばインドネシア語のアルファベット表記体系をオランダ人が作った時とか、ベトナム語のアルファベット表記体系をポルトガル人が作った時などにそのような現象が起きたそうです。
明治時代の”西洋かぶれ”の知識人達は、日本よりも西洋の方が”文明が進んでいる”のは、日本では膨大な数の漢字を習得するのに時間がかかるのに対して、西洋では少数のアルファベットを短時間で習得できるからである、したがって漢字を廃止し、ローマ字を国字にすれば西洋文明に追いつくことができる、という「ローマ字国字論」を主張しました。
仮にこの主張が認められて日本の国字がローマ字になり、漢字とカタカナとひらがなが廃止されたとします。 そしてその事情が全て忘れられてしまった後世に、明治時代以後のローマ字で書かれた文献を研究した後世の言語学者は、明治時代に存在したshi、chi、tsu、fu、jiという音が、わずか70年ほどでsi、ti、tu、hu、ziという音に変化してしまったと考えることでしょう。
ちなみに、ローマ字国字論は第二次世界大戦後にも流行します。 この時はGHQの命を受けたアメリカ教育使節団が、漢字の習得に時間がかかることが日本の民主化を遅らせている原因だから、漢字を廃止してローマ字を国字にするべきであると主張し、”進歩的かつ民主的(^^;)”なことを標榜する新聞社など多くのマスコミもこの主張に賛成しました。 しかし明治時代も第二次世界大戦後も、ローマ字国字論は民衆の支持を得られず、公認されませんでした。
おそらく飛鳥時代や奈良時代にも、ローマ字国字論と同じように、”唐かぶれ”の知識人達が「漢字国字論」や「万葉仮名国字論」を主張したのではないかと思います。 しかし当時の権力者が国の公文書を漢文と万葉仮名にしたのとは対照的に、民衆は漢字の一部を取ってカタカナを発明したり、漢字を崩してひらがなを発明したりして、漢字仮名混じり文という和唐折衷の表記体系を発明しました。
それと同様に明治時代にも、民衆はローマ字国字論を支持する代わりに、アルファベットやローマ字や外来語を独自の方法で消化吸収し、従来の表記体系にうまく取り入れて日本語の表現を豊かにしてきました。 これらはまさに、外来の文物をそのまま真似するのではなく、巧みに換骨奪胎して日本化することが得意な日本人の面目躍如たるところです。
「和製英語やカタカナ語は欧米では理解されないニセモノである、そのようなマガイモノの外来語は外国語の正しい習得を妨げ、美しい日本語が乱れるから排除すべきである! p(-"-)」
と主張する知識人が沢山います。 しかし中国から取り入れた漢字と多くの単語、そして和製漢字である国字は既に確固たる日本語になり、オランダやポルトガルの言葉を日本語化した外来語は既に立派な日本語になって日本語の表現を豊かにしています。 そしてそれらの漢字や外来語を使用したために、中国語やオランダ語やポルトガル語の正しい習得が妨げられたという話は聞きません。 (^^;)
そもそも現在では、漢字が中国から取り入れられたことはほとんどの人が知っているでしょうが、どの漢字が日本でできた国字であり、どの言葉が日本語化した外来語であるのかは知らない人が多いと思います。 しかしそれらの日本語化した外来語も、取り入れた当初は頭の固い知識人からニセモノとかマガイモノと非難され、「外国語の正しい習得が妨げられる!」とか「美しい日本語が乱れる!」と反発されたことでしょう。 (^^;)
和製英語もカタカナ語も日本に向くかどうかで取捨選択され、次第に日本語化して日本語の表現をより豊かにしつつあります。 これらの外来語は長い年月の間に淘汰され洗練されて、やがて日本独自の和洋折衷文化として定着していくことと思います。