地球外知的生命の探索のことであり、天文学、地学、物理学、生物学、化学など、自然科学のほとんど全ての領域を含んだ学際的な科学です。 SETIの最初の試みは、1960年に開始された有名なオズマ計画です。 オズマ計画はアメリカ国立電波天文台(NRAO)のフランク・ドレークが中心となって行ったもので、地球外知的生命からの通信を電波望遠鏡によって組織的に探索しようとするものでした。
この計画では地球に比較的近く、太陽に似た2つの恒星、エリダヌス座ε星とクジラ座τ星に電波望遠鏡を向け、中性水素原子の出す21cmの波長(宇宙で一番普遍的だと思われる周波数、マジック周波数と呼ばれます)の電波を探索しました。 この計画のことは、当時小学生だった僕もマンガ雑誌の記事で読んで知っていて(^^;)、胸をワクワクさせたことを覚えています。
残念ながらオズマ計画は具体的な成果を出せずに終わりましたが、その後も、派手ではないもののSETIの試みは絶え間なく続けられています。 また宇宙人からの信号を探索するだけでなく、人類の側から宇宙人にメッセージを送る試みもなされています。 1972年に打ち上げられたパイオニア10号と、翌1973年のパイオニア11号に宇宙人へのメッセージを刻んだ銘板が搭載され、1977年のボイジャー探査機に地球の音や映像を納めたレコード盤が搭載されたのは有名ですし、1974年にはプエルト・リコのアレシボ電波望遠鏡から、2進数にコード化されたアレシボ・メッセージが送信されています。
SETIには莫大な費用がかかる上、何となく雲をつかむような話で、実用的ではないためこれを専門とする科学者はあまり多くありませんし、日本には皆無と言ってもいいくらいです。 しかし、これほど好奇心を刺激するテーマはめったにありません。 我々はどこから来たのか、そしてどこへ行くのか、さらに我々は何者か、何をなすべきなのかといった、人類の過去・未来・現在のあり方に関わる、極めて根元的なテーマと言ってよいでしょう。
それでは宇宙人が存在する確率はどの程度あるのでしょうか? 銀河系の中に人類と交信可能な宇宙人がどれくらい存在しているかを見積もるものとして、有名なドレークの式があります。 この式は、1960年にグリーンバンク天文台で行われた地球外知的生命に関するグリーンバンク会議でドレークによって提唱されたものです。
N:交信可能な銀河内文明数
R:1年間に銀河系全体で生まれる恒星の数
fp:生まれた恒星が惑星を伴う確率
ne:生命の生存できる条件を備えた惑星の数
fl:そのような惑星上で生命が発生する確率
fi:発生した生命が知的な存在にまで進化する確率
fc:知的生命体が他の星に通信を送る技術を発達させる確率
L:そのような文明が実際に通信を送る年数
このように式そのものは単純ですが、各因子の値を正確に見積もることは難しく、この式の評価は非常に困難です。 例えばR=10、fp=0.5〜1、ne=1、fl=1、fi=1、fc=1、L=1〜1千万とすると、N=5個〜1億個となり、非常に大きな幅があります。 しかしまあ実用的な面はさておき、各因子に色々な値を代入し、宇宙人についてあれこれ夢想するにはなかなか面白い式だと思います。
SFの分野ではウェルズの「宇宙戦争」以来、宇宙人との接触は古典的なテーマの1つで、SETIが関係する作品もたくさんあります。 SF映画ではキューブリックの名作「2001年宇宙の旅」や、スピルバーグの意欲作「未知との遭遇」あたりがメジャーでしょう。 SF小説では、SETIを行っていた電波望遠鏡が恒星タウ・ケチから女性のすすり泣くような声の信号を捕らえるという非常に印象的なプロローグで始まる、ポール・プロイスの「天国の門」(早川書房)、自らもSETIを専門とする科学者で、アレシボ・メッセージに重要な貢献をしたカール・セーガンの処女作、「コンタクト」(新潮文庫)などが有名です。
「コンタクト」は科学者セーガンが書いただけあって、物語的な面では少々物足りないものの、科学的な面ではしっかりとした考察がなされています。 ただ僕が一番印象に残ったのは、日本に招かれた科学者達が日本料理を食べるシーンでした。(^^;)
ピタゴラスの定理(三平方の定理)で有名なピタゴラス(紀元前572年〜492年)を教祖とする、数学的・哲学的・宗教的・政治的結社で、万物は数であるという主張を中心教義としていました。 ピタゴラスはマッドサイエンティストの元祖のような人で、そのためピタゴラス教団も高尚な数学や哲学を研究するかと思えば、宗教的な儀式を行ったり、政治に口を出したりと、かなり矛盾した集団でした。
ピタゴラス教団ではそこで教わったことや発見されたことを教団外に口外することは固く禁じられていて、発見されたことは全て教祖であるピタゴラスの発見とされました。 しかも記録類を一切残さなかったので、ピタゴラスの色々な数学上の業績が本当にピタゴラス本人によるものかどうかは、実はあまり確かではありません。 特に三平方の定理はピタゴラスが生まれる1000年以上前から知られていたので、現在の数学界ではこの定理は「三平方の定理」と呼ばれることが多いと思います。
ピタゴラスの定理を証明したピタゴラスは、
「このすばらしい定理を思い付き、その証明に成功したのは、いつも自分を激励し、守って下さっている学芸の神ムーサのお陰である」
またピタゴラス教団の人達は厳格な菜食主義者でしたが、豆だけは食べようとしませんでした。 なぜなら彼等は、人が死ぬと霊魂は一旦豆に入り、次の転生先の準備ができるまで、しばらくそこに留まっていると考えたからです。
ピタゴラス教団の矛盾の最たるものは、皮肉なことにピタゴラスが最も自慢した三平方の定理に潜んでいました。 1辺の長さを1とする正方形では、その対角線の長さは三平方の定理から√2になります。 この√2という数字が(整数/整数)という分数の形では表せない無理数であることを、ピタゴラスの弟子が証明してしまったのです。 このことは「万物は数である」という中心教義を真っ向から否定することであり、ピタゴラス教団の内部に大きな衝撃を引き起こしました。
一説では無理数を発見した弟子は海につき落とされて溺死したとも、崖からつき落とされたとも言われています。 この説の真偽のほどは定かではありませんが、教団が無理数の秘密をひた隠しに隠そうとしたことは確かです。 しかしこの秘密は次第に外部に知られるようになり、やがて教団が崩壊する一因にもなっていったのです。
<参考>√2が無理数である証明
√2が有理数と仮定すると、共通因子のない整数pとqを用いて、
∴q2 = 2r2
数学的には螺線(ラセン、spiral)といい、極座標(r,θ)表示による方程式r=f(θ)において、fがθの単調関数になるような曲線のことです。 代表的な渦巻線として、自然界でよく見かける対数ラセンがあります。 対数ラセンは、
このラセンは拡大しても縮小しても元のラセンと重ね合わせることができ、フラクタルに通じるような自己相似性を持っています。 この性質が無限に成長するものを暗示しているように感じられるせいか、対数ラセンは別名永遠の曲線と呼ばれることもあります。
微積分に大きな貢献をした数学者のベルヌーイはこの対数ラセンを非常に気に入っていて、生前、自分の墓石には対数ラセンと、”Eadem resurgo(私は元どおり復活する)”という言葉を彫り込んで欲しいと遺言したそうです。 ところがベルヌーイが死に、墓石を作る時になって、数学をよく知らない石屋が対数ラセンではなくアルキメデスの渦巻線を彫り込んでしまったのです。
アルキメデスの渦巻線は、
熱力学の第2法則のことであり、高温の物体と低温の物体を接触させて自然のままに放置しておくと、熱は必ず高温の物体から低温の物体に移動し、その逆の過程は決して起こらない(クラウジスの原理)とか、単一の熱源からの熱を全て仕事に変換するだけで、他には何の変化も起こさずに周期的に作動する機関は存在しない(第2種永久機関不能の原理)とか、孤立系のエントロピーは不可逆変化によって常に増大するなどと表現される原理です。
暖かい部屋に氷を放置しておくと氷は融けて水になり、そのぶん部屋の温度がわずかに下がります。 その逆の過程つまり水が氷になって、そのぶん部屋の温度がわずかに上がるという現象は自然状態では決して起こりません。 熱力学の第2法則はそのような自然界の不可逆性を表わす法則です。
エントロピーというのは系のデタラメさ(無秩序性)を表す状態量のことで、ボルツマン定数をk、系のエネルギーがEの時の微視的状態の総数をW=W(E)とすると、次のようなボルツマンの関係式で表わされます。
例えば1組52枚のトランプがあり、それが種類ごとにA(エース)からK(キング)まで順番に並んでいるとします。 この状態は非常に整った状態ですから、エントロピーは低い状態にあります。 この1組のトランプをシャッフル(切り混ぜること)すると、種類や数字の順番は乱れてデタラメな状態になりエントロピーは増大します。
理論的には、偶然、最初と同じ整った状態になる確率もあるにはあります。 しかしその確率は非常に小さいので、普通はより確率の大きい現象──つまりデタラメになる現象が起きるのです。 これと原理的に同様のものがエントロピー増大の原理の統計力学的解釈であり、自然界における時間の進む方向──これを時間の矢といいます──と関係していると考えられています。
自然界の根本原理を反映していると思われる量子力学や相対性理論では、エントロピー増大の原理は説明できず、同時に時間が一方方向にしか進まないということも説明できません。 しかし現実の自然現象ではエントロピー増大の原理に反する現象も、時間が逆転して過去に戻るような現象も、今のところ観測されていません。 このあたりについては、ホーキング博士がその著書「ホーキング、宇宙を語る」と「ホーキングの最新宇宙論」(ともに早川書房)中で、ビッグバンによる膨張宇宙論と合わせて論じていて非常に興味深いところです。
時間の矢を決定しているのは一体何でしょうか? また時間とはそもそも何でしょうか? この素朴な疑問に答えてくれる人を、僕は昔から待ち続けています。
前項で説明したように、孤立系のエントロピーは増大し続け、最終的にはエントロピー最大の無秩序状態(熱死状態)になると予想されます。 しかし系の規模が大きい場合、局所的にエントロピーが低い状態を作ることにより、系全体のエントロピーがより速やかに増大することがあります。
例えば風呂桶から水を排出する時、渦巻きという局所的にエントロピーの低い秩序状態を作ることにより、渦巻きがない時に比べてより速やかに排水することができます。
また物質が酸化する時、炎という局所的にエントロピーが低い秩序状態を作ることにより、炎がない時——例えば鉄が錆びる時——よりも速やかに酸化が進みます。 物質が酸化するためには一旦エネルギー状態が高い反応中間体を形成し、それからエネルギー状態が低い酸化物に変化する必要があります。 炎はその反応中間体を形成するためのエネルギーを提供する場であり、それによって酸化反応が速やかに進むのです。
炎の代わりに通常よりもエネルギー状態が低い複雑な反応中間体を形成し、それによって化学反応を速やかに進ませる役目をする物質が触媒です。 生物は蛋白質によって形成された触媒の塊であり、化学反応を速やかに進め、その時発生するエネルギーで生命を維持しています。 そのことから生物とはエントロピーをより効率的に増大させるために発生した局所的にエントロピーが低い秩序状態であり、炎と同じようなものであると考えることができます。
炎が物質の供給を受け、物質が酸化して系全体のエントロピーを増大させるのを助けると当時に、酸化エネルギーを利用して炎自体を維持しているように、生物も物質を取り込み、それが化学反応を起こして系全体のエントロピーを増大させるのを助けると同時に、反応エネルギーを利用して生命を維持しているわけです。
事実、生物がいない状態よりも、生物がいる状態の方が系全体のエントロピーはより速やかに増大します。 そして生物の進化と呼ばれる現象は、基本的には系全体のエントロピーをより速やかに増大させる方向に生物の構造を変えていて、その最たるものが人類に他なりません。
そのように考えると、生物が環境を破壊してエントロピーを増大させるのは必然的な宿命であり、環境を破壊しては役目を終えて滅亡し、破壊された環境に適応した次なる生物が繁栄してさらなる環境破壊を繰り返し、エントロピー最大の熱死状態に向かって突き進むということになります。
一方、宇宙全体を閉鎖系と考えると、恒星や銀河というものは局所的にエントロピーの低い秩序状態であり、これらが形成されることによって宇宙全体のエントロピーがより速やかに増大していると解釈することができます。 実際、恒星とは原子力レベルの炎であり、これが形成されることによって物質がより速やかに熱エネルギーつまり光子に変わります。
また恒星が形成する銀河とは宇宙レベルの渦巻きであり、これが形成されることによって重力エネルギーがより速やかに熱エネルギーに変わります。 さらに太陽と惑星から形成される太陽系も銀河と同じような宇宙レベルの渦巻きであり、重力エネルギーを速やかに熱エネルギーに変換する役目を果たしています。
1960年代に、地球を巨大な生命体のようなものと考えるガイア理論またはガイア仮説が提唱されました。 これは地球と生物が相互に関係し合って環境を作り上げ、その環境を保持していく自己調整能力を持っていることから、地球全体を巨大な生命体のようなものと捉える理論です。 この理論はギリシア神話の女神「ガイア」にちなんだ印象的な命名と、エコロジーの流行によってマスコミでも盛んに取り上げられました。
地球も生物も系全体のエントロピーを効率的に増大させるために発生した、局所的にエントロピーの低い秩序状態だと考えれば、これらが相互に関係し合って秩序状態を維持していくのは当然です。 つまりエントロピーという面から見れば、生物も地球も恒星も銀河も、全て風呂桶の渦巻きや炎のようなものであり、
「消えろ、消えろ、つかの間の灯火……人生は歩きまわる影法師にすぎぬ」

 その5へ
その5へ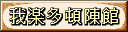
 webmaster@snap-tck.com
webmaster@snap-tck.com