
 その6へ
その6へ
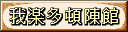
 webmaster@snap-tck.com
Copyleft (C) 2000 SNAP(Sugimoto Norio Art Production)
webmaster@snap-tck.com
Copyleft (C) 2000 SNAP(Sugimoto Norio Art Production)
SF作家アイザック・アシモフが提唱した、SFに登場するロボットが従うべき行動原理で、次のような内容です。
アシモフはロボット物を得意としていて、この三原則をメインテーマとした連作短編集「われはロボット」および「ロボットの時代」、忘れがたいロボット刑事R・ダニール・オリヴォーが活躍するSFミステリー、「鋼鉄都市」および「はだかの太陽」などの傑作を発表しています。(作品はすべて早川書房)
「われはロボット」以後のロボット物は、他の作者の作品でも多かれ少なかれこの三原則の影響を受けています。 例えば手塚治虫のマンガ「鉄腕アトム」でも、「ロボット法」という形で取り入れられています。 しかしアトム自身の行動原理はこの三原則ではなく、むしろガンディー翁の無抵抗主義を基盤にしていると、手塚治虫は語っています。 論理的でミステリータッチの「われはロボット」と、人間的でハートフルな「鉄腕アトム」との違いは、そのあたりにも原因があるのでしょう。
またもっとうがった見方をすれば、ロボットに対する考え方そのものが、欧米と日本では根本的に異なっているような気もします。 論理的な欧米では、ロボットをあくまでも人間に奉仕する機械にすぎない、と割り切って考えることが多いのに対し、森羅万象に八百万(やおよろず)の神を認める日本では、人間に対すると同じようにロボットに感情移入し、友達として考えることが多いのではないでしょうか?
アシモフのロボット物の中で僕が一番感動した作品が、「バイセンテニアル・マン(二百周年を迎えた男)」(短編集『聖者の行進』より、創元推理文庫)であったことも、そのことと無関係ではないように思います。 「バイセンテニアル・マン」は、ロボット三原則を乗り越え、人間らしくなることを切に望んだロボットの物語で、アシモフのロボット物とは思えないほど情緒たっぷりです。
アシモフのロボット工学三原則はかなり抽象的ですので、ロボットに限らず、もっと広く「テクノロジー三原則」とも、「サービス業三原則」ともとらえることができます。 そして、そこが作品を発想する上でのミソともなっています。 ちなみに「テクノロジー評価規準三項目」として、次のような項目が挙げられることがあります。
例えば自動車は作動原理が人間とは異なっていますので、人間との相性も、人間の住んでいる環境との相性もいまひとつ良くありません。 操作を覚えるのが難しく、特別な運転免許を必要としますし、地表をコンクリートで固め、人間の住む自然環境をガラリと変えてしまわなければ、性能を十分に発揮することができないのです。 この意味で、自動車はまだまだ未完成なテクノロジーと言えるでしょう。
コンピュータも作動原理が人間とはまったく異なっているため、人間との相性も、環境との相性もあまり良くないテクノロジーです。 しかしコンピュータはまだまだ発展途上であり、人間や人間の住む環境との相性を良くするような方向には向かっているようです。 将来的には、誰でもが体の一部であるかのようにコンピュータを使いこなすことができ、電話よりも気軽にコンピュータ通信ができるようになってくれたら、きっと便利で楽しいことでしょう。
一定の事実に関する記憶、またはある期間内の記憶が脱落する現象で、日本語では「健忘」といいます。 つまり平たく言えば、
です。 健忘は俗に言う記憶喪失のことですが、医学的には「記憶喪失症」という病名はなく、「健忘症」と呼ばれます。 巷で言われている記憶喪失症の状態──強いショックで過去の記憶を失い、記憶が戻ると、反対に記憶喪失だった時の記憶がなくなってしまう──は、健忘症というよりも、強いショックで脳震盪を起こし、一時的な意識障害を起こした状態と考えられます。
一時的な意識障害を起こした場合、脳の一部だけが覚醒していて、本人の意識はほとんど無いにもかかわらず、無意識的な反射だけで覚醒しているかのように振るまうことがあります。 例えば泥酔した時とか、ボクサーが半ばノックアウトされた状態の時がそれです。 この状態の時は本人の意識はほとんどありませんから、当然、過去の記憶は曖昧ですし、その時の行動を記憶することもありません。 そのため、本当に覚醒して過去の記憶を取り戻した時には、半覚醒中のことはほとんど覚えていないわけです。
記憶喪失は非常にドラマチックですから、多くの小説やドラマの題材にされています。 特に推理小説では頻繁に利用され、ビル・S・バリンジャーの「消された時間」(早川書房)などが有名です。 また個人の記憶喪失ではなく、人類全体の記憶喪失をテーマとしたSF小説に、菊地秀行の「風の名はアムネジア」(ソノラマ文庫)があります。 押井守監督のOVA「機動警察パトレイバー・その名はアムネジア」は、「風の名はアムネジア」の題名をもじり、内容は伝統的な推理小説タッチのパロディになっているので、大いに笑わされてしまいます。
人間の記憶というものは不思議なものですから、やはりドラマの題材になりやすく、記憶喪失以外にも、既視感(deja vu、初めて見る情景を過去にも同じように見たと錯覚すること)、既体験感(deja vecu、初めての体験を過去にも同じように体験したと錯覚すること)、未視感(jamais vu、過去に熟知していることを初めての経験と錯覚すること)などがよく使われるようです。
第一次世界大戦中の1915年、ドイツとフランスの国境付近でドイツ軍とフランス・カナダ連合軍が相対峙していましたが、双方とも決め手を欠き膠着状態になっていました。 同年4月22日夕刻、イープル西方の西部戦線で、突然、ドイツ軍の陣地から黄白色の煙が流れ出しました。 そしてこの煙が連合軍の陣地に達するや、たちまち連合軍将兵達の間に収拾のつかない大混乱が生じたのです。 煙を吸った将兵達はもだえ苦しみ、呼吸困難になって次々と死んでいき、それを見た他の将兵達は算を乱して退却しました。 この戦闘で連合軍の死者は約5000人、中毒者は約1万4000人に達し、ドイツ軍はランゲマルクの占領に成功しました。 こうして、膠着状態にあった西部戦線にひとつの突破口が開かれたのです。
これが人類史上初の本格的な生物化学兵器(Biological Chemical Weapons、BCW)が使用された有名なイープル戦で、使用された物質は窒息性の塩素ガスでした。 ちなみに、この戦線のことを題材としたルイス・マイルストン監督の名作「西部戦線異常なし」は、映画史上初の本格的な反戦映画として有名です。 塩素ガスは19世紀後半に興った染料化学工業や薬品化学工業の副産物として得られていたもので、ドイツ軍がその毒性に目をつけて兵器として利用したのです。
イープル戦をきっかけとして、各国ともガス兵器の開発に血眼となり、窒息性ガスのホスゲン(ギリシャ語で「光」の意味、クロロホルムに光をあてると発生することで有名)、血液毒の青酸(シアン化水素酸、探偵小説などでお馴染み)などが続々と開発されました。 第一次世界大戦で使用されたガス兵器は約30種類、研究されたものは約3000種類以上にものぼったということです。 その中でも、「マスタードガス」こと「イペリット」は特に有名です。
1917年7月12日の夜、最初のガス兵器が使用されたイープル戦線で、またしても不思議なガス兵器が使用されました。 ドイツ軍の手によって連合軍陣地にまかれたそのガスは遅効性であり、最後の散布が終わってしばらく経ってから、あたかも忍び寄るかのように、名状しがたい混乱が次第に連合軍の陣地に広がったのです。 このガスの最初の刺激は比較的弱く、しかも持久度が高いため、知らない間に目や皮膚がただれ、呼吸器が徐々に侵されます。 このため最初は皮膚病と誤認されたほどで、その正体が明らかになったのは1週間も経ってからでした。 この新しいガス兵器は糜爛性の硫化ジクロルエチルで、後にフランス軍はイープルの地にちなんで「イペリット(決してペリシットではない (^^;))」と呼び、イギリス軍はカラシ臭のあるところから「マスタードガス」と呼びました。
第一次世界大戦とは対照的に、第二次世界大戦ではガス兵器は公式には一度も使われませんでした。 枢軸国側(ドイツ・イタリア・日本)にせよ、連合国側にせよ、必ずしもガス兵器を使わないと決めていたわけではなく、大いに研究はしていましたが、ガス兵器は敵・味方ともに被害が大きくなりがちで、それを使うにはかなり思い切った決断が必要だったのです。
1930年頃、アスピリンで有名なドイツのバイエル製薬会社の付属研究所で、化学者J.シュレーダーを中心とする農薬開発グループが、ドイツの主要農作物であるジャガイモの寄生虫を駆除するために、新しい殺虫剤の開発に取り組んでいました。 彼等は数々の試行錯誤を重ねた結果、昆虫の堅いキチン質の隙間から体内に浸透し、神経系を侵して窒息死させる有機リン系の農薬を開発しました。 この有機リン系の農薬は人体に対しても強烈な毒性を持っていることがわかり、それを知ったナチスは即座にあらゆる資料の公表を禁止し、これを新型ガス兵器に応用することを命じたのです。
こうして、殺虫剤として開発された農薬は一瞬にして恐るべき毒ガスに転化しました。 そして第二次世界大戦が終了するまでに、約2000種類の有機リン化合物が合成され、タブン、サリンなどの強力な神経性ガスが生み出されたのです。
これらの毒ガスは兵器として実用化段階にまでこぎつけていましたが、時すでに遅く、これらを使う機会のないまま、1944年にナチス・ドイツは敗北しました。 ナチス・ドイツの敗北後、ドイツ軍の研究施設を接収した連合国側の関係者は、従来のガス兵器とは比べものにならない威力を持つこれらのガス兵器に驚嘆し、「Gガス(German Gas)」と呼びました。 第二次大戦後、Gガスを出発点としてますます強力なガス兵器が開発される一方、本来の開発目的である農薬としての研究も進められました。 現在使われている多くの有機リン系農薬は、ほとんどがこのGガスを母体としています。
| 名称 | 化学構造式 | 種類 | LD50(mg/m3) |
|---|---|---|---|
| 塩素 | Cl2 | 窒息性 | 3200 |
| ホスゲン | COCl2 | 窒息性 | 3200 |
| 青酸 | HCN | 血液毒 | 2600 |
| イペリット | (ClCH2CH2)2S | 糜爛性 | 1500 |
| タブン | C2H5・(CH3)2N・P・O・CN | 神経性 | 400 |
| サリン | (CH3)2CHO・CH3・P・O・CN | 神経性 | 100 |
生物化学兵器の研究と生命科学の研究は、原理的に同じものを研究対象としますから簡単に相互転化することができます。 多少なりとも生命科学に関わっている人間として、複雑な思いを抱かずにはいられません。
去勢とは、弱い人間が見栄を張って自分を強く見せること……というわけではなく、雄の精巣(ヒトでは睾丸)や雌の卵巣の機能を抑制し、性ホルモンの分泌を止めて、性衝動や性能力を喪失させることです。 去勢が重要な意味を持つのは雄の方ですから、去勢と言えば普通は雄の去勢を指します。 去勢には次のような種類があります。
性衝動も性能力も喪失しないので本来の去勢ではない。
家畜の去勢はほとんどがこの方法である。
性衝動だけは残るため、非常におぞましい結果となる。 陰茎を梵語(サンスクリット語)で「魔羅(マラ)」と言うことから、この方法を「羅切(ラセツ、ラギリ)」と呼んだ。
いわゆる「パイプカット」。
家畜の場合はほとんどが幼去勢であり、ヒトの場合は多くが熟去勢である。 幼去勢は第2次性徴が現れないか、不完全となるので、ヒトの場合は特別な意味を持つ。
睾丸を除去する方法としては、次のようなものがあります。
……だんだんと書くのがつらくなってきましたが (^^;)、気を取り直して解説を続けますと、これらのうち一番多いのは1番の摘出法で、摘出した睾丸はモンゴルなどでは有名な睾丸料理にし、日本ではもったいないことに捨てているそうです。
幼去勢すると声変わりしないことを利用して、ボーイソプラノをそのまま維持した特殊な歌手を去勢歌手(カストラート)といい、17〜18世紀にローマ教皇の教会を中心としてヨーロッパ各地で活躍しました。 このことは最近「カストラート」という映画にもなったので、御存知の方も多いでしょう。
去勢歌手はオペラでも活躍するようになり、大作曲家であるヘンデル、グリック、モーツァルトなども去勢歌手のためにオペラを作曲しました。 例えばモーツァルトの名作「フィガロの結婚」に登場する、小姓ケルビーノ(有名な「恋とはどんなものかしら」を歌う役)はそもそも去勢歌手の役でした。 またヴェルディやシュトラウスのオペラで、少年や若い男の役であるにもかかわらず、現在、女性歌手が演じている役は、かつて去勢歌手が演じていたことの名残です。
後年、オペラから去勢歌手が衰退した後も、ローマ教皇の教会はいつまでも去勢歌手を抱えていて、最後の去勢歌手アレッサンドロ・モレッグスリィ・エイミスの晩年の歌声が古いレコード(ロウ管)に残っているそうです。 残念ながら僕はそのレコードを聞いたことはありませんが、どこかにあれば一度は聞いてみたいもんです。