
 4へ
4へ
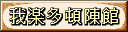
 webmaster@snap-tck.com
Copyleft (C) 2000 SNAP(Sugimoto Norio Art Production)
webmaster@snap-tck.com
Copyleft (C) 2000 SNAP(Sugimoto Norio Art Production)
ダンスパーティーはそれから9時過ぎまで続いた。 その間、みんなが色々な組み合わせで踊ったけど、僕等はなるべく雪子さんと正氏の組み合わせができないように気を配っていた。 もっとも僕と伴ちゃんは、何しろダンスができない上に生まれて初めての経験なもんで、「壁の花」ならぬ「壁のシミ」になってることが多かったけどね。
パーティーが終わり、みんながそれぞれの部屋に引き取ってしばらくたった頃、僕の部屋に雪子さんがやって来た。 耕平氏が、僕等と話がしたいから書斎に来て欲しい、と言うんだそうだ。 いよいよおいでなすったか……! と緊張が走ったけど、幸いなことにミミちゃんと伴ちゃんが一緒でも構わないからということで、四人で揃って敵陣に乗り込むことになった。 人数が多い方が何かと心強いし、ミミちゃんという強力な味方が付いていることで随分と気が楽になった。
もう10時に近かったし、さっきまで降り続いていた激しい雨もようやく止んでいたので、別荘の中はひっそりと静まりかえっている。 二階から降りてホールに入ると、コックの大野さん達がまだダンスパーティの後片付けをしていた。 さっきまで華やかな雰囲気が満ち溢れていただけに、半分ほど片付けられたホールはちょっとうら寂しい感じがする。
ホールを通り抜け、展覧室の隣の書斎に行くと、耕平氏がやけに優しく招き入れてくれた。 書斎はけっこう広くて、真中に豪華な応接セットがデーンと置いてあり、入口から向かって左の壁には渋い色をした本棚がずらりと並んでいる。 その本棚には大小様々な本がびっしりとつまっていて、いかにも書斎にふさわしい雰囲気をかもし出している。 僕がざっと視線を走らせたところでは、やはり美術関係の本が多く、見慣れた文庫本やマンガなんかは(当たり前の話だけど)まるっきり見当たらなかった。 応接セットの後には木目の浮いた素晴らしくりっぱな机と、皮張りのゆったりした椅子があり、机の上には昼間見た手さげ金庫がフタを開けたまま置いてあった。 金庫にはふちすれすれのところまで浮世絵が入っていて、机の上にも一枚の浮世絵が出ている。
耕平氏は僕等をソファーに座らせると、雪子さんに飲み物を出すように言いつけてから机のところに行った。
「ちょっと、絵の点検をしていたもんでね。 日に一度はこいつらを見ないと、どうも落ち着かんのだな、はははは……」
と弁解がましく説明しながら、彼は机の上の浮世絵を取り上げて金庫にしまい、それが最後の一枚だったらしく、そのままフタをして金庫を机の隅に押しやった。 それからもみ手をしながら戻って来ると、ソファーにゆったりと腰をおろし、にこやかな顔つきで僕等を見回した。
「夜分に呼びたてたりしてすまなかったね。 ちょっと話したいことがあってね」
どうも気味が悪いくらい愛想が良い。 この愛想の良さがクセ者なんだろうと、こっちは耕平氏の笑顔に反比例して緊張の度合いが高まっていく。
「他でもない、雪子のことなんだよ。
荻須君、君は一体どういうつもりで雪子と付き合っているのかね?」
「は?
ど、どういうつもりで、と言いますと……?」
「こういうことは、はっきりしといた方がいいと思ってね」
耕平氏の表情は最初と変らずにこやかだったけど、僕を見つめる目に鋭い色が漂い始めた。
「雪子も薄々感づいているようだから、君も聞いたかも知れんが、今回はうちの雪子と笹岡さんの御子息を引き合わせようとして、この別荘に御招待したんだ」
耕平氏の目の色がさらに鋭くなり、強い光を帯びてきた。 僕はうなずくこともできず、黙って話を聞いているしかなかった。
「それを雪子が、まるで対抗するように君を招待したいと言いだし、君もこうしてここに来ているわけだから、それなりの覚悟があってのことなんだろうね?」
「……覚悟、と言いますと……?」
返事をする前に思わずゴクリと唾を飲み込み、その音が相手まで聞こえたような気がして、ますます緊張してしまった。
「とぼけちゃいかんよ、君。 雪子と一緒になる気があるのか、と聞いとるんだ!」
とうとう耕平氏はにこやかな仮面をかなぐり捨てて、真剣な表情となった。 その鋭い視線に射すくめられて、僕は口が乾き切って唇が歯にくっついてしまい、うまくしゃべることもできなかった。
「は、はあ、それは、その……」
「友規君は単なるボーイフレンドよ、そんなこと聞くなんて失礼だわ、お父さん!」
ありがたいことに、お盆に飲み物を乗せた雪子さんが部屋に戻って来ていた。 飲み物をみんなに配りながら、彼女は父親をたしなめるような目で睨んだ。
「単なるボーイフレンドをわざわざこんな所まで招待したのか、お前は?」
「ええ、そうですよ。今の若者は、昔と違ってフランクで進んでるのよ」
「嫁入り前の娘がそんなふしだらなことでどうする。
世間体ってもんも少しは考えたらどうだ」
「また、そんなー……。
あたしはまだ誰とも結婚する気なんてありませんって言ったでしょ?
友規君は単なるボーイフレンドで、今度のことは何も知らないのよ」
雪子さんは僕に顔を向けて、申しわけなさそうに言った。
「ごめんなさいね、友規君。
あたしが悪いのよ、何も知らない友規君を勝手に利用しちゃったりして……」
「何言ってんだよ、ちゃんと話してくれたじゃないか!」
雪子さんにあんな顔であやまられて、僕も黙ってるわけにはいかなかった。 そこで耕平氏を見ながら、きっぱりと言った──つもりだったけど、正直言って少し震え声になっていたようだ。
「持田さん、雪子さんはそんな勝手な人じゃないですよ。
ちゃんとわけを話してくれたもんですから、二人で相談してこうしたんです」
「あたし達みんなで相談してね、友規君」
と、ミミちゃんが注釈を入れた。 彼女は穏やかな面持ちで、いつもの茶目っぽさこそ影をひそめていたものの、緊張した様子はさらさらなかった。
「あたし達4人で相談したんです、持田さん。
ほんとはあたしが最初に雪ちゃんから話を聞いて、それでこの二人に相談を持ちかけたんです」
「やはりな。
大方、そんなことだろうとは思っとったんだが……」
耕平氏は目の光を少しやわらげて、雪子さんを見た。
「雪子、わしだって何も今すぐ笹岡さんと結婚しなさい、なんて言っとるわけじゃあないんだ。
ただ結婚を前提としてちょっと付き合うなり、そういった相手として考えてみるなりしてくれんか、と言っとるだけなんだよ」
「ですから何度も言ってるように、あたしはまだそんな気にはなれません、お父さんにはお気の毒ですけどね」
雪子さんはうんざりしたような、そしてかすかに皮肉っぽいところも感じられるような口調だった。
「別に、わしが結婚させたがっとるわけじゃあない。 笹岡さんがお前を気に入られて、御子息の相手として考えてみたいから、ぜひにと頼まれたんだ」
ここで耕平氏は、僕にジロリと鋭い視線を送り、
「まあ、わしもまだ早いとは思うんだがな、大学で変な虫が付いてもいかんと思って、一応紹介だけでもと引き受けたんだ」
なるほど耕平氏にしてみれば、どこの馬の骨とも知れない僕なんて、大事な娘に取りつくダニのようなもんなんだろう。 しかしそうは思っても、いくらしがないサラリーマン風情の息子とはいえ、僕にだって一応プライドってもんが(ほんのちょっぴりだけど)ある、内心ムッとして耕平氏を見返した。
それに気づいたのか、雪子さんが代りに怒ってくれた。
「変なムシはあの正って人の方でしょ、友規君はりっぱな紳士よ。
お父さんは自分の会社にとって都合がいいものだから、無理矢理、あんな人を押しつけようとしているだけなんだわ」
「そんなことはない。わしは、ちゃんとお前のためを思って……」
「口先だけよ、そんなこと。
お父さんは会社のことしか頭になくて、人を見る目がないのよ」
「そんなことはないと言っとるだろう。
わしが何も知らないとでも思っとるのか?
お前がこっそり中川と付き合っとることぐらい、わしにはちゃんとわかっとるんだぞっ!」
耕平氏の言葉にも、すでにそれを予期していた雪子さんは少しもひるまなかった。
「中川さんだってちゃんとした紳士よ。
あんなプレイボーイ気取りのドラ息子なんかより、よっぽどりっぱだわ。
お父さんは会社のためには自分の娘を餌にしたって平気で、あたしのことなんてどうだっていいんだわ!」
「な、何だとっ!?」
と怒鳴るなり、耕平氏はいきなり立ち上がって、
「こ、このわしが、お前を餌にするだと!? お、親に向かってその口のきき方は何だっ!」
耕平氏は真赤になって雪子さんを睨みつけた。 握りしめた両手がブルブルと小刻みに震えている。 雪子さんの膝の上に置かれた手も白くなるほど握りしめられ、やはり少し震えているけど、顔は敢然と上を向き、父親をキッと見すえていた。 しっとりとして優しげに見えた彼女の、どこにこんな強いところがあったんだろうかと、目を疑ったほどのりりしさだ。
この緊迫した場面に、突然、伴ちゃんがボソボソとした口調で雪子さんに語りかけた。
「あ、あの、持田さん、悪いけど、ぼ、僕、持田さん、間違ってると思います……」
「えっ!?」と、雪子さんがびっくりした顔で伴ちゃんを振り返った。
「な、何言いだすのよ、伴ちゃん!」
ミミちゃんもさすがに慌てた様子だ。
「ごめんね、僕、関係ないのに、口出ししちゃって……」
伴ちゃんは、頭をかきながら申しわけなさそうに言った。 その態度には、いつものように誠実さが溢れている。
「でも、つい、黙ってられなくて……。
持田さん、いくら腹立っても、お父さんにそんなひどいこと言ったら、いけないんじゃないかな、持田さんらしくないですよ」
「そ、それは……」
「それに、あの正って人も、今日会ったばかりなんだから、プレイボーイだとか、ドラ息子だとか決めつけるのは、やっぱり、良くないんじゃないですか?」
「それはそうだけど、でも……」
とつとつとして、真実味溢れる伴ちゃんの言葉に、雪子さんの口調はしだいに弱くなっていった。 でも、目だけはまだ毅然として父親を見すえている。 僕とミミちゃんはわけがわからず、伴ちゃんの顔を見つめるばかりだ。
「き、君は、いいことを言ってくれた!」
耕平氏は思わぬ味方を得て、我が意を得たりとばかりに喜び勇んだ。
「何て名前だったか忘れてしまったが、彼の言うとおりだ、雪子。
付き合ってみんことには、どんな人かもわからんだろう、どうだ?」
「あ、あの、も、持田さんのお父さん、それは無理だと思います、僕」
雪子さんが答えるよりも早く、伴ちゃんがまたボソッと言った。 その態度には、雪子さんに対すると同様にやはり誠実さが溢れている。
「無理!?
それは、一体どういうわけかね、君?」
「だ、だって、持田さんって、すごく正直で、すごく素直な、ものすごくいい人ですから。
こ、心から好きな人がいるのに、別の人と付き合うなんてこと、できっこないですよ」
「中川君のことかね、君の言うのは?」
「は、はい。
も、持田さんのお父さんだって、中川さんのこと、気に入ってるんでしょ?」
「ええっ、わしがか!?
と、とんでもない、あんな男!
どうしてわしが、あんな男を気に入らなゃならんのだっ」
「だ、だって、態度見てれば、わかりますよ、そんなこと。
だ、だいち、気に入ってるからこそ、重要な仕事任せたり、大事な絵の管理、頼んだりしてるんじゃないですか?」
「そ、それは……、それとこれとは、話が別なんだ」
耕平氏は戸惑ったように、ゆっくりと腰を下ろした。 そんな耕平氏の態度を見て、僕はびっくりしてしまった。 ひょっとしたら、伴ちゃんの言っていることが当たらずとも遠からずってとこなのかも知れない。
「べ、別じゃないですよ。 中川さんって、すごく責任感の強い、ほんとにいい人ですし、持田さんとも、うらやましいぐらい、信頼し合ってるんです」
伴ちゃんは、急に改まった様子で耕平氏に向き直ると、
「お、お願いします、持田さんのお父さん、な、中川さんと話し合ってみて下さい。 持田さんと三人で、話し合ってみて下さい、どうか、お願いします」
誠実そのものの伴ちゃんの態度だった。 まるで自分のことのように一生懸命に頼み込む伴ちゃんの姿に、耕平氏はあっけにとられたように黙ってしまった。
「あたしからもお願いします、持田さん。 いっぺんでいーですから、雪ちゃんと中川さんの話を聞いてやって下さい、ぜひお願いします!」
ミミちゃんも伴ちゃんのひたむきさに感動したのか、いつになく真剣な態度だ。 僕も黙っているわけにはいかず、二人と同じように耕平氏に頼み込んだ。
「僕、僕もお願いします。 ほんとは、僕は雪子さんの単なる知り合いで、雪子さんは、中川さん以外の人なんか目に入らないぐらい真剣なんです」
雪子さんは僕等の方をまじまじと見つめ、
「ありがとう……みんな……」
とつぶやいたきり、うつ向いてしまった。
そんな僕等の嘆願をどう受けとめているのか、耕平氏は苦虫をかみつぶしたような顔で、黙然と腕を組むと、何事かじっと考え込んでいる様子だった。