
 第1章へ
第1章へ
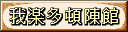
 webmaster@snap-tck.com
Copyleft (C) 2000 SNAP(Sugimoto Norio Art Production)
webmaster@snap-tck.com
Copyleft (C) 2000 SNAP(Sugimoto Norio Art Production)
「ねえ、荻須君、恋人になってくれない?」
「えーっ! こ、こ、恋人に……!?」
僕はハトが豆鉄砲を、それもソラ豆みたいなやつをくらったような顔をして(た、と思うよ)、しばらく口がきけなかった。 だって当たり前でしょ? 何てったって小山内ミミと言えば我がクラスの、いや理学部のアイドル、元美少女スターの「南井操ちゃん」なんだし、僕ときたら、平々凡々、どこにでもころがってるごく普通の学生なんだから。
デビューしたての中学生頃から、南井操はお気に入りの美少女俳優だったんだ。 清純可憐な笑顔と愛くるしくキュートな目が最大のチャームポイントで、明朗快活、眩しいほどの若々しい活発さが内気な僕にはたまらない魅力だった。 若者なら誰でも、僕のように内気な若者ならなおのこと、絵にかいたような青春ドラマにのめり込む時代があるもんで、憧れているだけでとても現実にはならない、 熱い願望を満たしてくれる主人公達と一体化してしまって、同じように喜んだり苦しんだり、時にはドラマの中のマドンナに恋してしまったりするもんだと思う。 操ちゃんはそんなマドンナ達のひとりで、僕だけじゃなく僕の友人達の間でもけっこう人気があった。
ところが高校生になり、ますます美少女になった彼女の人気が急上昇し始め、いよいよこれからという時、突然、彼女は芸能界を引退してしまい、ファンの前からフッツリと姿を消してしまったんだ。 一時は週刊誌なんかでも「南井操、謎の引退!」なんて騒がれたりしたほどで、引退の理由は誰にもわからなかった。
それが東横大学の理学部に入学してみてびっくり、何とその操ちゃんそっくりの美少女が同じクラスにいたんだ!
もちろん最初の頃は、よく似た別人だろうとみんなが思っていたし、その当人、つまり小山内ミミ嬢もそんなことはおくびにも出さなかったけど、そのうちに、どうやら本当にかつての「南井操」その人らしいという噂が広がり始めた。 物好きにも昔のゴシップ雑誌から操ちゃんに関する記事を探し出してきた奴がいて、その記事によると、「南井操(みないみさお)」という芸名は本名の「小山内(おさない)ミミ」のアナグラム、つまり文字を並べ変えて作ったものだということなんだ。
ほどなく、小山内ミミ嬢と親しくなった女の子によって、やっぱり彼女は南井操その人だったということが確認されたけど、どういうわけか彼女はそのことにあまり触れられたくない様子で、ここだけの秘密にして欲しいとのことだった。 でもいつの世でも、「ここだけの秘密」ってやつは「公然の秘密」に早変わりするもので、あっという間にクラス中から理学部中、さらに大学中に知れ渡り、たちまち彼女は理学部のアイドル、我がクラスのヴィーナス、そりゃあクラスは言うにおよばず、理学部中の野郎どもは目の色変えて彼女とお近づきになろうとしたもんだ。
おかげで彼女の出席する講義には受講希望者が殺到し、先生は嬉しい悲鳴、僕等のクラス独自の講義にさえ他のクラスの学生が押しかけて、僕のように内気な学生は隅に追いやられ、肩身の狭い思いをしている始末。 とにかくえらい騒ぎなんだけど、こちとらハナっからお近づきになろうってな野望はあっさり(というと嘘になるけど)捨て、「フン、たかが元美少女スター、どうってこたァないネ」なんて、やせ我慢もはなはだしい言い訳を我と我が身につぶやいて、通りいっぺんの挨拶程度しか言葉を交せないでいたんだ。
それが夏休みを間近にひかえた7月の初め、僕と親友の伴ちゃんがいつものように学生食堂でA定食を食べていたら、突然、そのミミ嬢が目の前に腰掛け、モナリザみたいな謎の微笑みを浮かべて、事もあろうにこの僕に恋人になって欲しいと言ったんだ!
「ううん、そーじゃないの」
ミミ嬢は僕の表情を読み取ったのか、さとすように、
「あたしの恋人に、じゃなくって、あたしの親友の恋人に、なのよ」
なァーんだ……僕は落胆の色を見せまいと、隣の伴ちゃんの方に顔を向けた。 伴ちゃん、女の子の前だといつもそうなんだけど、少し顔を赤らめ、ポケーッとした表情で僕を見返すばかり。
彼、伴ちゃんこと四条伴人君──柄にもなく、シジョウトモヒトって読むんだよ──こそは、変人揃いの理学部にあってもそれと知られた抜群の変人、3、4年にひとりくらいは必ず入学して来る、いわゆる「ミスター理学部」なんだ。 スズメも夜逃げしそうなボサボサ髪、人類というよりは猿類に近い容貌、小柄で短足ガニ股という貧相な肉体的特徴に加えて、四季を問わずすり切れたジーパンに下駄ばき、黄色だかベージュだか、はたまた──多分、これが本当のところだと思うけど──汚れだかわからない色した、シワシワのカッターといういでたちが、ただでさえ不浪児じみた風貌に一段と真実味を加えている。
でも彼の言動にはどこかしら人を引きつけるところがあり、特に思わずこちらもつり込まれてしまう、はにかみがちな人懐っこい笑顔と、少年のようにどこまでも透き通った瞳は、一目見たら好きにならずにはいられないような不思議な魅力を持っていて、誰からも好感を持たれているし、僕とはやたらとウマが合い、一番の親友になってしまった。 純情素朴ではにかみ屋、熱中型で忘れん坊、天才的なヒラメキとすごい科学知識を持っているくせに、世事に疎く、世の中の事は自分の鼻先に来ても──多分、実際にブチ当たっても──気がつかないほどなんだ。
「わけ話さなきゃ、わかるわけないわよねー。実はね……」
と、ミミ嬢が真顔になって説明してくれたところによると、何でも彼女の親友の持田雪子ってコが、これが有名な持田電気って会社の社長令嬢で、会社のために、やっぱり有名な笹岡自動車って会社の社長令息と無理矢理交際させられようとしているらしい。
「つまり、よーするに政略結婚の犠牲ってわけ」
何だか小説じみててウソみたいな話なんだけど、さらに輪をかけて、お定まりの「親に許されぬ心に決めた恋人」ってのが父親の会社にいるんだそうな。 親も薄々それに感付いていて、こりゃあ早く手を打たねばと、この夏休みに伊豆の別荘に笹岡家を招き、それとなくお見合いをさせようって魂胆らしい。 正式なお見合いじゃなく、親同士だけがそのつもりで、本人達は単なる社交上の紹介にすぎないと思っているという、よくあるアレらしい。
どうしたら良いかと相談されたミミ嬢、そりゃあ何とかしなくっちゃてんで、
「でね、誰かニセの恋人連れてって、お見合いブチ壊そうってことになったのよね。 だって恋人の中川って人、雪ちゃんの父親の会社の社員なもんで、何かと具合悪いでしょ? それで、荻須君にそのニセの恋人役やって欲しいってわけ」
と相なった次第。
伴ちゃんほどじゃないけど僕も世事には疎い方なもんで、やれ政略結婚だ、お見合いだって言われても、ほとんどピンとこないし、有名な会社だか何だか知らないけど、はっきり言って持田電気も笹岡自動車もまるっきり聞いたこともない。 でもせっかく憧れのミミ嬢が説明してくれたんだから、さも納得したような顔して、
「なるほどね、話はわかったけど、なんで僕なんかに?
他に、もっとらしい人いるでしょーに」
「らしくない方がいいのよ、『あんな娘じゃ困る!』って、相手から断らせるよーに仕向けなきゃならないんだから。
それに……」
と、ミミ嬢は操ちゃんだった頃の人気の一因だった、愛くるしくキュートな笑顔を僕に向け、
「荻須君なら安心なのよね。 何てったらいーか、こう、絶対、間違っても変なふーになる心配ない、大丈夫だって。 とにかく、安心してられるのよね」
何じゃそりゃ、どういう意味じゃ!? 結局、僕は三枚目のシラノ役ってわけ? そりゃあ確かに二枚目じゃないのは自他共に認める僕だけど、そりゃないよねえ……と思ったら、すぐそれと察したのか、ミミ嬢に先手を打たれてしまった。
「あ、誤解しないでね、それだけ信用してるってことなんだから」
ミミ嬢、今度は一転して大真面目な顔になって、
「だってそーでしょ、雪ちゃんにしてみたら、一生の大問題よ。 人柄が良くって、トコトン信用できる人じゃなきゃ、こんな大事なこと頼みっこないわよ。 ……ね、そーでしょう、伴ちゃん?」
と、隣の伴ちゃんに視線を移した。 意見を求めるというよりは、どうしてもウンと答えなさい、と言わんばかりの視線だ。 伴ちゃん、ミミ嬢に見つめられ、真赤になりながら口の中でモゴモゴと答えた。
「……う、うん、と、友規なら、だ、大丈夫、絶対、信用できるよ」
人見知りが激しい伴ちゃんは、普段はとつとつとしてポツリ、ポツリしゃべるんだけど、あまり親しくない人と話す時には少し吃りがちになり、それが女の子だったりしたら吃りに吃る上、小声でやたらと早口にしゃべるもんだから、何を言っているのかほとんど聞き取れない。 僕も最初の頃は戸惑ったけど、慣れというものは恐ろしいもんで、今じゃあ伴ちゃんの言ってることがはっきりと聞き取れるようになった。 それどころか伴ちゃんの顔色を見ただけで、どんなことを考えているのか手に取るようにわかってしまうんだ。 もっとも、純情な伴ちゃんは喜怒哀楽がそのまま顔に出るタチなので、しゃべってる言葉はわからなくても、言わんとすることは誰でも大体察しがつくみたいだけどね。
「でしょ? そー思うでしょー?」
よしよし、いい子いい子、といった感じで伴ちゃんにうなずきかけると、ミミ嬢は一転して僕にすがるような目を向けた。
「ね、お願い、荻須君!」
何だか、誉められてんのか、けなされてんのかよくわからないけど、クラス中の憧れの的、小山内ミミ嬢その人に頼まれたんだから、もちろん悪い気がするはずもない。
「それほど見込まれたんなら、喜んで引き受けるけど、そんなお金持ちの別荘なんて今まで行ったことないから、中でどうすりゃいいのかよくわからんよ、僕」
「大丈夫、大丈夫、地のままやってくれたらいーのよ。
それに、あたしも伴ちゃんも一緒だから」
「イッ! ぼ、僕も一緒!? い、一緒って、ど、どうして、僕が……?」
てっきり自分は関係ないと思っていた伴ちゃん、口をアングリ開けてミミ嬢を見つめた。
「モチのロン、あたしのボーイフレンド役よ。 健全なる大学生といたしましては、グループ交際がトレンディーなのよね、あたしひとり、アブれるわけにはいかないもん」
ミミ嬢は、1たす1が2になるがごとく、さも当然といった口調。 僕は思わず御飯を丸呑みにし、伴ちゃんにいたってはドンブリまで丸呑みしたような顔して目を白黒させている。
「あたしのボーイフレンド役じゃ、役不足?」
「い、いえ、そ、そんな……」
「そ、じゃ、OKね。
さあ、これで主役と脇役も決まったし、みんなで爽やかな青春ドラマにしましょーね!」
と言うと、ミミ嬢はこぼれんばかりのキュートな笑顔を僕等に向けた。
そしてこれが、あのとんでもない事件に僕と伴ちゃんが巻き込まれてしまった、そもそもの発端だったんだ……!