
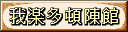
 webmaster@snap-tck.com
Copyleft (C) 2000 SNAP(Sugimoto Norio Art Production)
webmaster@snap-tck.com
Copyleft (C) 2000 SNAP(Sugimoto Norio Art Production)
次の日の昼過ぎ、僕と伴ちゃんとミミちゃんは持田家の別荘に別れを告げた。 たった四日間だというのに、あまりにも多くの出来事があったもんだから、僕は別荘に不思議な愛着を感じてしまって、何となく名残惜しい気持ちになっていた。 そしてそんな気持ちになっていたのは僕だけじゃなかったようで、伴ちゃんもミミちゃんも、いざ出発する段になって別荘の外に出た時には、感慨深げな目で別荘を眺めていたもんだ。
笹岡家の人達は、僕等より一足先に別荘を後にしていた。 その時、ちょっと面白いことがあったんだ。 別荘の玄関前で持田家の人達と一緒に彼等を見送っていた時、僕等と一緒にいた雪子さんのところに裕美さんが近付いて来て、ニンマリしながらこう言ったんだ。
「おめでとう、雪子さん。
ちょっとくやしいけど、あなた達の勝ちみたいね」
「え…?」
「あなたと中川さんのことよ。
彼、カッコいいもんね、あたしだってシビレちゃったわよ。
うちの兄貴なんかとは雲泥の差だわ」
「えっ!?」
「とぼけなくてもいいのよ、二人でお幸せにね」
裕美さんはいたずらっぽい視線を雪子さんに投げかけ、
「グズグズしてると、あたしが取っちゃうから。 ……じゃーね、バーイ!」
と言い残すと、親達の待つ車の方に飄々と歩み去った。 雪子さんはそんな彼女の背中に向かって、
「さようなら!」と声をかけ、それから真面目な顔で、「ありがとう、裕美さん……」と静かにつけ加えた。
雪子さんは中川さんの運転する車で僕等を駅に送って来て、プラットホームまで見送ってくれた。 プラットホームに上がると、列車が来るまでまだ時間があったので、ミミちゃんは強引に伴ちゃんを付き合わせて、お土産や列車の中で食べるおやつを買いに駅の売店に向かった。 別荘でのお芝居の名残か、ミミちゃんと伴ちゃん、雪子さんと僕という組み合わせで行動するのが、何となく癖になってしまったようだ。
「ほんとに不思議な人ですねぇ、伴ちゃんて……」
まるで修学旅行の女学生みたいに、大はしゃぎしながらお土産を物色しているミミちゃんと、相変わらず戸惑いがちに彼女に付き合っている伴ちゃんを眺めながら、雪子さんがしみじみとした口調でポツリと言った。
「え?」
「ミミちゃんからね、伴ちゃんのこと聞かされた時、本当にそんな人がいるのかしらって、信じられない気がしたんですよ、あたし」
「そんな人って?」
「まるで星空みたいに純粋で、切なくなるぐらいひたむきな人だって……。
ミミちゃんったら、会うたびに伴ちゃんの話ばっかり」
「そうですか……」
「おかげで、本人に会う前からだいたいのイメージは持っていたんですけど、正直言って、半信半疑なところもあったんですよ」
「で、どうでした、実際に会ってみて?」
「ホントーにいたんだなあって。
このあわただしい世の中に、こんな人が存在していたんだって、そりゃあもう、びっくり」
「天然記念物ですね、まるで」
「それぐらいの価値ありますよ、あの人には」
「確かに……」
「ミミちゃんが、一度会えばすぐわかるからと言っていたわけが、やっとわかりました。
実際に会うまでは、誰だって信じられませんよね、あんな人がいるなんて」
「ちょっと口では言い表せないような人柄ですからね、伴ちゃんは」
「思っていた以上に、不思議で素晴らしい人でした。
ミミちゃんが惹かれるわけが、よくわかります」
「え?」
「気づいてないんですか?
あんなに見え見えなのに……」
雪子さんは、むしろ意外そうな表情で僕を見た。
「自分ではあれでも隠しているつもりなんでしょうけど、ミミちゃん、根が正直だからすぐ顔に出てしまうんですよね」
気づかなかったわけじゃなかった、気づいていたんだ、僕だって。 ただ、信じられないって気持ちと、信じたくないって気持ちとが入り混ざり、はっきりさせるのが怖くて、わざと考えないようにしていたんだ。 かつての憧れの的、操ちゃんが男の子を好きになってしまったなんて、そんなこと信じられない、いや信じたくない……こんなファンとしての嫉妬心と、素顔のミミちゃんにも新たな魅力を感じ始めていた僕の、男としての嫉妬心が、誰からも好かれる伴ちゃんの人柄にかこつけて、目の前の明白な事実から目を背けさせていたんだ。
雪子さんにはっきり言われて、ようやく自分の狭い心に気がついた僕は、たまらなく恥ずかしくて、雪子さんの顔をまともに見ることができなかった。
「そうだったんですか、やっぱり……」
「最初の日に、海岸でミミちゃんの失恋の話をしましたよね?
その時、あのコが今回のことを荻須さん達に相談した理由を、『荻須さん達と親しくなるきっかけ作りのため』だって言いましたけど、あれ、本当は半分しか説明してなかったんですよ」
「半分しか、と言いますと……?」
雪子さんは困ったような微笑みを浮かべて、ミミちゃんと伴ちゃんに意味ありげな視線を送り、その視線をまた僕に戻した。
「……わかりますでしょ? 本当に、荻須さんには何と言ってお詫びしたらいいのか、わかりませんのですけど……」
そこまで言われて、ようやく雪子さんの困ったような微笑みのわけがピンときた。
「なるほど、そーですか、そーだったんですかぁ……。
これでよーやく、ミミちゃんが僕をニセの恋人役に抜擢した、本当の理由が納得できましたよ」
「どうか気を悪くしないでやって下さいね、あのコも必死だったんでしょうから」
「何言ってんですか、大喜びですよ、僕は。
いっぺんに二組のカップルのキューピット役ができたなんて、友達冥利につきるってもんですよ、ほんとに」
「そう言ってもらえると、あたしも気が楽になります。
何しろミミちゃんって、いじらしいほど純なところがありますから、何とかうまくいって欲しいって、そればっかり思ってて……」
「そりゃあ、伴ちゃんも同じですよ。
これからもよろしくお願いしますよ、二人のこと」
これは冗談でも負け惜しみでもなく、今の僕の本当の気持ちだった。 狭い嫉妬心から、伴ちゃんに対するミミちゃんの気持ちをわざと考えないようにしていたけど、こうしてそれをはっきり認めてしまった今は、かえってすっきりしてしまったんだ。 そして二重の意味でとんだ三枚目役をやらされたってのに、二人の愛すべき性格のせいか、ちっとも嫌な気はしなくて、むしろ心の底からニッコリできるような、そんな微笑ましい気持ちで一杯だった。
僕と雪子さんがニッコリと顔を見合せていると、両手一杯にお土産やらお菓子やらを抱えてミミちゃんと伴ちゃんが戻って来た。 ミミちゃんは僕等二人の和やかな雰囲気に気づいたらしく、
「あら、やに嬉しそうね、二人とも。
まさか、お芝居が本気になっちゃったんじゃないでしょーね?」
「ん?
いやいや、そんなんじゃないけど、何となく嬉しくてね。
事件も見事に解決したし、雪子さん達もうまくいったし、まるで青春ドラマを見終った時みたいな、清々しい気分だよ」
「そりゃそーよ、何てったって、かの美少女スター南井操が監督した青春ドラマだもん、最後は爽やかなハッピーエンドに決まってるじゃない!」
と言って、ミミちゃんはこぼれんばかりのキュートな笑みを満面にたたえて、心底気持ち良さそうに僕等の顔を見回した。
そしてこれが、二組のカップルのキューピット役というひどく間の抜けた役どころを、心ならずもこの僕がやらされてしまった、とんでもない事件の顛末なんだ……!