
 エピローグへ
エピローグへ
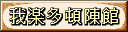
 webmaster@snap-tck.com
Copyleft (C) 2000 SNAP(Sugimoto Norio Art Production)
webmaster@snap-tck.com
Copyleft (C) 2000 SNAP(Sugimoto Norio Art Production)
「さあ伴ちゃん、僕等には本当のことを話してくれるんだろーね。 まさか、あんなデタラメな推理で、この僕を納得させれるとは思ってないよね?」
夕食後、中川さんから言われて、僕と伴ちゃんとミミちゃんは僕の部屋に集まり、幸せそうに顔を輝かせた雪子さんと、楽しげな中川さんの訪問を受けていた。
「デタラメって、友規君、それどーゆー意味!?」
「荻須さん、あの説明が間違っているとでも言うんですの?」
ミミちゃんと雪子さんの怪訝そうな視線を受けても、僕は自信満々だった。 今度は僕がみんなを驚かす番なんだ。
「実をゆーとね、一昨日の晩、僕は、生まれて初めてベッドなんかで寝たもんだから、あんまり良く眠れなくて、夜中に何度も目を覚してたんだよ」
次の言葉の効果を高めようと、僕はここで言葉を切って、みんなの顔をグルリと見回した。
「でね、3時頃にも一度目を覚したんだけど、その時、雨なんか一滴も降ってなかったよ!」
「……!!」
ミミちゃんと雪子さんが目を丸くして僕を見つめているのを意識して、僕は少々得意な気分だった。 伴ちゃんはホッとため息をつくと、中川さんと視線を交わし、意味ありげにニッコリとした。
「よかったよ、起きてたのが友規だけで……。
ほんと言うと、誰か目を覚してた人、いるんじゃないかと思って、ヒヤヒヤしてたんだ」
「だから、僕が言っただろ?
みんな酒が入っていたし、パーティーで疲れていたはずだから大丈夫だってね。
でも、まさかベッドのせいで眠れない人がいるとは、夢にも思わなかったなあ、はははは……」
と、中川さんも安心したように笑った。
「えーっ!?
……じゃ、じゃあ、あの話はみんなデタラメなの!?」
「ひっどいわ、伴ちゃん、いっくらなんでも、あんまり水臭いじゃない!」
雪子さんがびっくりした表情で中川さんの顔を見つめ、ミミちゃんも同じような顔で伴ちゃんを見つめた。
「すまない、すまない、僕が悪いんだよ、四条君のせいじゃないよ、小山内さん。 僕が口止めしてたんだ、本当に申しわけないっ!」
と中川さんは、雪子さんとミミちゃんに向かって手を合せた。 伴ちゃんもミミちゃんと僕にかわるがわる顔を向けて、
「ごめんね、ミミちゃん、それに友規も……。
ほんとは、二人にだけは、こっそり話すつもりだったんだけど、いいタイミングがなくて……。
ごめんね、ほんと」
「そんな……、いーのよ、別に。
別に、怒ってるわけじゃないんだから……」
中川さんにも伴ちゃんにも素直にあやまられたもんだから、ミミちゃんはあっさり機嫌を直してしまった。
「実はね、みんなに本当の事を話そうと思って、こうして集ってもらったんだよ。
四条君の希望とはいえ、あんなふうに全部僕の手柄のようにしてしまったことも、心苦しく思ってたしね」
「そんなことないですよ、僕は、ただヒントを思いついただけで、謎を解いたのは、ほんとに中川さんですから」
「とんでもない、全て君のおかげさ。
ま、とにかく話してあげなよ、四条君」
「はい、じゃ……」
伴ちゃんはどうやって話そうかしばらく考えてから、やがてボソボソと話し始めた。
「夕べ、みんなで色々話し合ってた時、僕、2つの仮説を思いついたんだよ」
「2つもォ!?
あたしたちは、ぜーんぜん思いつかなかったのにー」
と、もうすっかり機嫌を直したミミちゃん、感心した顔つきで伴ちゃんを見ている。
「うん。
1つは、さっき中川さんが説明したやつで、夜中にまた雨が降って、ドロボウの足跡を消しちゃったってので、もう1つが、これから話すけど、正解だったやつなんだよ」
「あれも、やっぱ、伴ちゃんが考えたわけ?」
「うん。
でもね、あれにはちょっと難点があって、多分、もう1つのほうが、可能性が高いだろうって思ってたんだよ」
「夜中に、雨なんか降らなかったってこと?」
「いいや。
僕は、友規と違って、グッスリ眠ってたもんで、夜中に雨が降ったかどうか、知らなかったんだけど、そうじゃなくて、それ以外にもあるんだよ、難点が」
「何かしら、難点って?
あの推理は、雨のことさえなければ完壁に思えましたけど……」
不思議そうにそう言った雪子さんだけじゃなく、僕にもミミちゃんにも、その難点なるものは思いつかなかった。
「だって、ぬかるんだ地面を歩いた靴で部屋に入ったら、当然、ドロのついた足跡か何かが、そこら中につくはずでしょ?
窓のところで靴脱いだり、ドロ落としたりしたんなら別だけど、ドロボウがわざわざそんなことするなんて、あんまり考えられないもんで、多分、これは正解じゃないなって思ってたんだよ」
「あっ、そーか!
そーいえば、書斎には、そんなドロの足跡なんかなかったんだからなあ……」
僕は夕べの中川さんの説明を思い出して、思わずそう言った。 これは考えてみれば当然のことで、中川さんが説明した時に、誰もこの点に気づかなかったのが不思議なくらいだ。 あの時は、みんな中川さんの見事な話術に引き込まれてしまって、ついついすらすらと納得させられてしまったんだろうし、それがまた中川さんの狙いでもあったんだろう。
「うん。
ただ、これは、夜中に雨が降ったかどうか確かめれば、それではっきりすることだから、今朝、気象台に電話してみたんだよ。
そしたら、やっぱり、雨なんか降らなかったって言うんだよね」
「それが夕べ言ってた、確かめたいことだったんだな」
「それで伴ちゃん、それ確かめるまでは、みんなに話したくなかったのね」
僕もミミちゃんも、夕べの伴ちゃんの態度をようやく納得できた気がしてうなずいた。
「うん。
ただね、夕べみんなに話せなかったのは、ちょっと別の理由なんだけどね……」
「別の理由?」
「うん、それは、もう1つの答と関係してんだよ」
「正解だったやつね。それ、一体、どーゆー方法なの?」
僕等はもう今更新しいことを考えようとは思わず、ただただ伴ちゃんの答が聞きたかった。
「それはね、この建物に出入りした跡もなくて、この建物の中にもないんだったら、最初っから、絵なんかなかったんじゃないかってことだよ」
「えーっ!?」
と、僕等は異口同音に叫んだ。
「な、何言ってんだよ、伴ちゃん。
ちゃんとあったじゃないか、みんな、手に取って見たじゃないか!」
「昼間はね。
でも、あの後、あの絵を見た人、いないんだよね、ほんとは」
「そんなことないわよー!
だってあたし達だって、あの晩、書斎で雪ちゃんのお父さんが、絵調べてるとこ見てたじゃないの!」
ミミちゃんはキツネにつままれたような顔だ。 雪子さんも怪訝そうな表情だったし、僕だって伴ちゃんの言う意味が理解できなかった。 あの時、この目で確かに絵を見たんだ!
「ほんとうに、見た?
ちゃんと、全部あるとこをだよ?」
「え?
だって、ちゃんと手さげ金庫に入ってたし、机の上にだって出てたじゃない」
と、ミミちゃんはまだキツネにつままれた表情のままだ。
「うん、机の上の一枚と、手さげ金庫の中の、一番上の一枚は、確かに見たね。
でも、それ以外の絵は、見なかったでしょ?
残りの絵は、当然、金庫の中だって、思い込んでただけじゃないの?」
「……!」
ようやく僕にも、チラッとだけど光明が見えてきた。 あの時、金庫のふちすれすれまで浮世絵が入っているように見えたけど、浮世絵の台紙がちょうどスッポリと金庫に収まるようになっているので、よく考えてみれば一番上しか見えてなかったんだ。
「そーいえば、あの時、金庫の中まで見たわけじゃないね……」
「でも……、でも、あの時、金庫一杯だったわよ、確かに」
「上げ底だったんだよ。
下に、本かなんかを2、3冊置いて、その上に1、2枚絵を乗せれば、下まで全部入ってるように見えるもんね」
「そーかっ!
それで書斎に浮世絵が3枚残されてたんだ、最初っからあの3枚しかなかったんだっ!!」
僕は思わず声を上げて叫んでいた。 ミミちゃんも、目を見開いて伴ちゃんの顔を見つめている。
「そうなんだよ。
それで、一昨日、この別荘から出て行ったのは、たったひとりだし、その人は金庫に細工できる、ただひとりの人だし……」
「あたしの父ね、その人って……」
つぶやくように言った雪子さんの顔は、驚きと戸惑いの入り混ざった、何とも形容しがたい表情だった。
「……うん。 ごめんね、持田さん、だから僕、夕べ、はっきり話せなかったんです。 それに、どうして持田さんのお父さんが、そんなことする必要があったのか、全然わかんなかったし……」
これでようやく僕等にも、伴ちゃんが話せなかった本当の理由を理解することができた。 金庫にそんな細工ができるのは耕平氏以外にないし、そんなことを雪子さんの目の前で言えるわけはない。 それにしても、わかってしまえば何とも他愛のない解答なんだけど、これもやっぱりコロンブスの卵で、あまりに簡単過ぎて、天才にしか見抜けないことなのかもしれない。
「そーか、よーやく僕にもわかりかけてきたよ。
しっかし、さすがは伴ちゃん、よくそんなこと思いついたなあ……」
「そんなことないよ、誰でもわかることだよ、こんなこと」
「そーゆーわけだったのね……」
ミミちゃん、伴ちゃんを非難してしまったことを恥じているのか、伏目がちに伴ちゃんの顔をうかがいながら、しおらしい口調で言った。
「ごめんね、伴ちゃん、あたし、そーとは知らないもんだから、伴ちゃんのこと水臭いなんて思っちゃったりして……」
「いいよ、いいよ、そんなこと。僕こそあやまらなきゃ……」
伴ちゃんも僕等に申し訳なく思っている様子で、盛んに頭をかきながら、
「ごめんね、ほんと。 二人には話すつもりだったんだけど、なかなかチャンスがなくて……」
この時、今まで傍観していた中川さんが、ニコニコして口をさしはさんだ。
「まあ、それで今朝、気象台に確認を取った四条君は、すぐ僕に相談してくれたというわけさ」
「僕が考えたのはそこまでで、後は、中川さんが全部考えたんだよ。
ほんと、中川さんって、ものすごく頭が良くて、何でもわかっちゃうんだもんね、びっくりしちゃったよ、僕」
「おい、おい、四条君、そりゃあ皮肉に聞こえるぜ。
そこまでわかれば、後は誰だってわかることさ。
もっとも、動機なんかは純真な君には思いつかないことかもしれないが、僕のように、世間ずれした不純な人間にはわかるもんなのさ」
と言って伴ちゃんを恥ずかしがらせておき、中川さんは僕等に向かって説明を始めた。
「あの日、社長が会社に行ったことはわかっていたし、あれほど大事にしている浮世絵を、そこらあたりの、人目につくような場所に隠しておくはずはないから、今日、会社に行って心当りを調べてみたんだ。
そしたら、案の定、社長室の金庫に隠してあるのを見つけたってわけなのさ」
「それで秀昭さん、夕食の前に書斎で父と長いこと話しこんでたのね?」
そのことを知っていたらしく、雪子さんは納得顔で言った。
「そうなんだ。 会社で2、3疑問な点を確認して、この事件の全体像がほぼ理解できたので、四条君と一緒に社長と話し合いにいったのさ。 社長も内心困っていたらしくて、僕等の言うことを認めて、素直にあやまってくれてね。 それで三人で相談して、あんなウソッパチをでっち上げて、この事件をなかったことにしようとしたんだ」
僕にも事件の全貌が何となくわかってきたけど、もう少し詳しい話を聞きたいと思って、中川さんに言ってみた。
「なるほど……。
でも、僕にはまだ色々わからないことがあって、事件の全体像がつかみきれないんですが……」
「よし、それじゃあ、この事件の成り立ちを最初から説明しようか?」
「お願いしまーす!」
僕とミミちゃんは口を揃えて言った。 雪子さんは、無理もないことだけど、沈んだ様子で下を向いて話を聞いている。
「動機は後で話すけど、とにかくある理由から、社長は狂言ドロボウを思いついたんだな。
あの浮世絵が盗難にあって、2、3日して、この付近からまた発見されるようにしたかったんだ。
ところが、大切な浮世絵を、たとえ少しの間とはいえ、危険な場所に放っておくわけにはいかず、安全な場所に隠そうとしたのさ」
「それが、会社の社長室の金庫だったってわけですね?」
「そうなんだよ。
そこで秘書のひとりに、一昨日の昼頃、別荘に電話を入れるように、あらかじめ指示しておいたんだ」
「ああ、それで、あんなにタイミング良く急用の電話があったんですね」
「そのとおり。
で、一昨日の昼会社に行くと、浮世絵を隠して、また別荘に戻って来たんだ。
そしてあの手さげ金庫の細工をすると、夜になって君達を呼び、わざと金庫を開けておいて、浮世絵のあるところを見せ、証人を作ったというわけさ」
「じゃあ、あの話し合いはそれが目的だったのね!?
ひどいわ、お父さんったら……!」
雪子さんが顔を上げ、憤慨した口調で言った。
「いやいや、それだけじゃなくて、本当に君達と話し合いたかったんだよ。
ま、一石二鳥だったわけさ。
証人は君達じゃなくても、例えばこの僕でも誰でも良かったんだが、たまたま君達と話し合いたいと思っていたとこだったらしくてね」
「そうかしら……。
でもひどいわ、ミミちゃん達があんなに一生懸命説得してくれたのに」
「あの時は、社長も本当に心を動かされたんだと思うよ。
ま、その話は後でまたするとして……」
中川さんは先を急ぐように説明を続けた。 雪子さんに、色々と考えさせたくなかったのかもしれない。
「君達が書斎を出て行くと、社長はすぐに手さげ金庫を壊し、部屋を荒して窓を割り、ガラス切りを窓の下に落としておいたんだ」
「ひぇっ!
持田さん、あの後、すぐ書斎に細工をしたんですか?」
僕はさすがに驚いて、叫ぶような口調になってしまった。
「そう、その時がチャンスだったんだな。
僕はパーティーの後片付けで隣の管理室にはいなかったし、書斎に誰かが入ってくるような気遣いはなかったし。
夜中にやろうとすれば、寝室を抜け出す時、ひょっとして一緒の部屋の奥さんが目を覚すかもしれないし、管理室で寝ている僕に気付かれるかもしれないしね」
「そうなのね?
どうりで秀昭さんが、夜中に何も気づかなかったはずねえ」
雪子さん、中川さんに落ち度がないとわかって、ホッとした様子で彼を見た。 中川さんは肩をすくめて、
「まあね。
でも、もし夜中にやったとしても、気づいたかどうかわからないけどね」と軽く受け流し、「ところが、ここで少し計算違いが起こったんだよ」
「計算違い?」と、今度はまた僕が尋ねた。
「昼間の雨さ。
あの雨のおかげで、窓の下と書斎の中にドロボウの足跡をつけなけりゃならなくなったんだが、窓から出て別荘から遠くまで歩いて行き、また書斎に戻って来て、泥靴の足跡をつけるような時間もなかったし、誰かに気付かれる危険も多かったので、跡はつけられなかったんだ。
だいたい、書斎の窓からこっそり別荘に出入りするのは、なかなか大変だからね」
「そういえば、別荘の外から見ると、あの書斎の窓って僕の首ぐらいの高さがありましたもんね。
あれ見た時、こんな所から別荘に侵入するのはけっこう面倒だろうなと、僕も思いましたよ」
「うん、そうだね。
もちろん、雨は昼から降っていたから、書斎の中にドロボウの足跡をつける必要があることには気付いていて、それ用に物置にあった古靴を使おうと思っていたんだが、夜になって雨がやんでしまったので、別荘の外にも足跡をつける必要ができてしまったんだ。
しかし、さすがにそこまでやる時間はなかったんだね」
「じゃあ持田さんは、こんな不思議な状況になることを覚悟してたんですか?」
「いや、ここでまた計算違いが起こったのさ。
普段だったら、昼頃に白石さんが書斎を掃除することになっていたから、本当はその時盗難が発見されるはずで、あんなに朝早く発見されるはずじゃなかったんだな」
「そーいえば、白石さんが中川さんを6時に起こして、その時、偶然盗難を発見したんでしたね」
「そうなんだ。
社長としては、昼までには足跡の偽装工作をして、古靴をどこかに処分することもできるだろうし、別荘に出入りする人もいるだろうから、うまくいけば足跡が目立たなくなるかもしれないと思っていたんだね。
ところが意外にもあんなに早く盗難が発見されて、足跡をつけることができなくなってしまったんだ」
「なるほど、それであんな不思議なことになっちゃったんですねぇ。
なるほど、これでようやく、窓の外にも書斎にも足跡がなかったわけが納得できましたよ」
「そういうことだね。
それから、ガラス切りを窓の下に落としておいたのは、偽装としては下手な小細工だが、そんなものをいつまでも持っていると危険だから、そうやって処分するしかなかったんだな」
「そりゃそーでしょうねぇ。
もしそんなものを持ってるとこを警察に見つかったら、たちまち狂言ドロボウだってわかっちゃいますもんね」
「うん、そのとおりだね。
ま、そんなわけで、偶然こんな不思議な事件になってしまって、当の社長が一番困っていたわけさ。
何しろ、本当は2、3日したら、この別荘付近から盗まれた浮世絵が発見される予定だったんだが、警察にあれほど徹底的に捜された後で、ひょっこり見つかるのもおかしいし、別荘から離れた場所から発見されるにしても、どうしてそこにあったのか理屈がつけられなくてね」
「そこへ、中川さんと伴ちゃんが話し合いにいったわけですね?
だったら、持田さんにとっても救いの神だったかもしれませんね」
「僕もそう思うな。
社長も、単純な狂言ドロボウのつもりが、えらくオオゴトになってしまって、今さら真相を暴露するわけにもいかず、ひどく困っていたらしいからね」
「でも、なぜ父がそんなことを……?」
という雪子さんの質問に答える前に、中川さんはしばらくためらい、やがて言葉を選びながらゆっくり答えた。
「……それはね、君のためなんだよ、雪ちゃん」
「あたしのため!?」
「そうなんだ。
君を僕から取り戻そうとしたんだな、社長は」
「あなたから、取り戻す……?」
「君を手放したくなかったのさ、社長は。
今度のお見合いの件だって、実はそれが目的で、君を笹岡さんの息子さんと付き合わせる気なんか、最初からなかったんだよ」
「えっ!?
だって父は、あたしにあの正って人と付き合えって……」
「社長は、あれでなかなか人を見る目は確かでね。
君があの笹岡さんの息子さんなんかとは付き合う気がないことを承知で、笹岡さんからの話を引き受けたんだよ。
そうすれば、僕が君のことをあきらめるだろうと思ってね」
「あたしにはよくわからないわ、父の考えが。
だって、この話は自分の会社にとって都合がいいから、無理にあたしに勧めたんだと……」
「とんでもない、その反対さ。
僕があきらめさえすれば、社長はすぐにでもこの話を断わるつもりだったんだよ、娘がどうしても嫌がっているとか何とか理由つけてね。
そうすれば、会社にとっては多少マイナスになるだろうけど、君のためにはそんなこと覚悟の上だったんだ」
「そんな……、そんなこと信じられないわ、あたし。
だったら、なぜこんな狂言ドロボウなんかしたの?」
「それはね、思いがけず君が荻須君達を招きたいと言いだして、自分からこのお見合いを壊しにかかったからさ」
「えーっ!
僕等のせいなんですかァ!?」
これには僕もいささか驚いてしまった。 まさか、自分達がこの事件の動機に一枚からんでいるとは、思いもよらなかったんだ。
「そうさ。
このままではお見合いをツブされてしまうと考えた社長は、狂言ドロボウを思いついて、僕に責任を感じさせ、自分から身を引くよう仕向けたわけなんだ」
「なるほど、中川さんも、昨日、そのつもりだって言ってましたからね」
「まあね。
ただ、社長は会社まで辞めさせるつもりはなくて、雪ちゃんのことをあきらめてくれればそれでよかったんだがね。
社長としては、僕の態度を見極めてから、浮世絵が発見されるようにしたかったわけさ」
何ともないような顔で淡々と説明する中川さんを見つめながら、雪子さんはどういう顔をしたら良いのかわからないような、戸惑った表情で言った。
「本当に、ごめんなさいね、秀昭さん。
……でも、なぜ父がそこまであなたのことを嫌っているのか、あたしにはわからないわ。
だって最初の頃は、父もあなたのことを、なかなか見どころのある男だって、誉めてたぐらいなのよ」
「うん。
こんなこと言ってはなんだが、僕は社長には割とかわいがってもらってた方なんだよ、実際。
ただ、だからこそ、君とのことを知った時には、飼い犬に手をかまれたような、裏切られたような気がしたんじゃないのかな。
社長、口にこそ出さないが、君のことをずいぶん可愛がっているしね」
「そうかしら……。
確かに小さい頃はずいぶん可愛がってくれてたけど、大きくなってからは、そんな記憶ないけどなあ……」
「そんなことないさ。
社長、会社でも、暇な時にはよく君の話をするんだぜ。
あまり自分から自慢話のようなものはしないんだが、人から君のことを誉められると、すごく嬉しそうな顔をするんだよ」
中川さんはちょっと言葉を切り、テレ隠しのように肩をすくめた。
「ま、社長と僕は、君に関していわば一種のライバルみたいなものだから、僕にはよくわかるのさ、社長の気持ちがね」
雪子さんはうつ向いて、黙って中川さんの言葉を噛みしめていた。 その様子は、まるで内なる声にじっと耳を傾けているかのようでもあった。 ややあって、
「……そうね、きっとそうね、秀昭さんがそう言うんだものね」
とつぶやくと、迷いから覚めたようにきっぱりと顔を起こし、
「父が秀昭さんに対してやったことは、絶対許せないけど、一昨日の晩、あたし、父にあんなひどいことを言ってしまって、悪かったと思うわ。 会社のために娘を犠牲にするような父じゃないってわかったし、それに、父に焼きもち焼かれるなんて、ちょっぴり嬉しい気がしないでもないのよ、本当は」
最後は少し微笑んでいた雪子さんの顔を見て、中川さんは安心したようにうなずいた。
「僕も、それでいいんだと思うよ。
僕は、今度のことは、もうそれほど気にしちゃいないし、それに今度のことでようやくふんぎりがついたんだ」
「ふんぎりがついたって?」
「会社を、持田電気を辞めるってことさ」
「えーっ!!」
と、僕等は驚きの声を上げた。
「なぜ? なぜなの!? だって、もうそんな必要ないのに、どうして?」
雪子さんはまた悲しげな表情になって、中川さんの顔をうかがった。
「秀昭さん、ひょっとして、父に愛想をつかしたんじゃ……」
「そうじゃないさ!」
と快活に言うと、中川さんは明るい笑顔を雪子さんに向け、
「四条君の言ったとおり、僕には、こんな仕事は向いてないんじゃないかと思ってね。
実はね、僕の大学の先輩で、東京で探偵事務所をやっている人がいてね。
それで、前々からやってみないかって誘われていたんだが、色々あってなかなかふんぎりがつかなくてね」
「すごい、すごい!
中川さん、それいーですよ、僕は大賛成だなぁ」
「あたしも、大賛成!
中川さん、夕食の時、カッコよかったもん!」
「ぼ、僕も、いいと思います。
中川さんなら、絶対、ぴったりだと思います」
僕等三人は口々に賛成した。 中川さんの昔の夢は、スポーツ選手か警官になることだったそうだから、多少職種が違うとはいえ、またその夢を追うことになるんだし、彼なら必ずうまくいくような気がするんだ。
「ありがとう。
実は僕も、今では多少自信がないでもないんだよ。
何しろ、僕には四条君という秘密兵器があるからね。
難事件に出くわしたら、すぐ相談にいくから、どうかよろしくお願いしますよ、四条君」
「は、はあ、そりゃあ、もちろんいいですけど、僕なんか、あんまりあてにならないですよ……」
「いいや、充分あてにしてますよ。
なにせ、こっちは生活がかかってるからねえ、あははは……」
中川さんはそう言ってほがらかに笑い、僕等もつられて笑った。 でも、雪子さんだけは笑わず、不安げに中川さんの顔を見つめていた。
「じゃあ秀昭さん、父の会社辞めて、そこに……?」
「うん。
今度のことでようやく決心がついたんだ、君とのことも含めてね」
「……?」
雪子さんは中川さんの真意をつかみかねている様子だ。
「つまりね、何て言えばいいか……、要するに、決心したんだよ」
急に中川さんは、自信なげな、落ち着かない態度となってしまった。
「つまり、待っていてくれないか?
君はまだ若いんだし、僕にそんな資格が無いことはよくわかっているんだが、きっと一人前になってみせるから、それまで待っていて欲しいんだ」
「秀昭さん……!」
「自分に自信が持てたら、必ず、堂々と申し込みに来るから。
絶対、それだけは約束するよ。
と言っても、もちろん、君の気持ち次第なんだが……」
今度は、中川さんが不安げに雪子さんを見つめている。
「秀昭さん……」
雪子さんは中川さんの手を優しく取ると、恥じらいがちな小声で、
「あたし、今すぐだって、全然かまわないのよ」
と頬を染めて、何かを待つようにそっと目を伏せた。
「雪ちゃん……!」
中川さんも顔を赤らめて雪子さんを見つめ、今にも肩を抱こうと手を上げかけた時、ミミちゃんがコホンと咳ばらいをして、
「さあ、じゃ、伴ちゃんと友規君、ちょっとあたしの部屋に来てくれない?
大事な話があるんだ」
「えっ?
あっ、すまない、すまない、つい……」
僕と伴ちゃんが返事をする前に、中川さんが先に我にかえってしまい、
「いいんだよ小山内さん、僕はもうそろそろ部屋に戻るから」
と言いながら、彼は恥ずかしそうに頭をかいている。 それでも雪子さんは、上気した顔のまま中川さんの手を離そうとはしない。
「いーんですよ、あたし達、オジャマ虫のよーですもんね」
「そ、そんなことないさ。
……ま、とにかくそういうことで、それもこれも、みんな君達のおかげなんだ。
改めてお礼を言わせてもらうよ。ありがとう、三人とも」
「あたしからも、お礼を言わなきゃね」と、雪子さんも改まった態度で、「ありがとう、伴ちゃんに荻須さん、それにミミちゃんも。
ミミちゃん、本当に素晴らしい人達を連れて来てくれたわね」
そんな雪子さんに、ミミちゃん、得意げな表情でこう答えた。
「ね、言ったとおりでしょ? かの美少女スター南井操監督の青春ドラマに、ミスキャストなんてあるはずないのよね!」