
 4へ
4へ
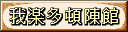
 webmaster@snap-tck.com
Copyleft (C) 2000 SNAP(Sugimoto Norio Art Production)
webmaster@snap-tck.com
Copyleft (C) 2000 SNAP(Sugimoto Norio Art Production)
昼食後、雪子さんの誘いで、僕達四人は別荘の前の海岸で海水浴をすることになった。 雪子さんは父親から笹岡家の人達のお相手をするように言われたんだけど、自分のお客の相手をしなきゃならないからと断わったんだ。
よしよし、我々の「お見合い粉砕大作戦」はなかなか順調に進行しているようだぞ!
ここに来る前に、ミミちゃんから、海水浴もできるから水着を持ってくるように言われていたので、僕も伴ちゃんも一応用意はしてあったんだけど、肉体美にはほど遠いおのが肉体を、うら若く美しい女性の前にさらすのはやっぱり気後れがしないでもない。 それにひきかえミミちゃんと雪子さんは、さっきの食事の反動もあるのか、子供のようにはしゃぎまわっている。 意外なことに、ミミちゃんは小柄ながらなかなか見事なプロポーションの持ち主で、はちきれんばかりの若々しい魅力を惜しげもなく発散しているし、雪子さんはスラリとした長身を上品な水着に包み、長い黒髪を潮風になびかせて、これまたしっとりと落ち着いた女らしい魅力に溢れている。
そんな二人の姿がまぶしくて、めったにないチャンスだというのに、僕はまともに二人を鑑賞することもできず、やたらと砂浜ばかり眺めていた。 こんなことをうちのクラスの連中に言ったら、罵詈雑言、非難の集中砲火を浴びることは目に見えている。
「お前が見る見ないはどーでもいーが、何だって写真1枚撮ってこんかったんだァ!?」
なんて声が今にも聞こえてきそうだ。 大学ではミミちゃんの隠し撮り写真が密かに──と言っても、昔のファンの間では半ば公然にだけどね──出まわっていて、一部の熱狂的なファンの間ではべらぼうな高値を呼んでいるらしいんだ。 ミミちゃんの水着のスナップ写真なんていったら、血みどろの争奪戦が繰り広げられることは火を見るよりも明らかだ。
ただ前々から僕は何となく後めたいような、クラスメートとしてミミちゃんに悪いような気がして、なるべくそんな写真は見ないようにしてきたんだ。 これは──もちろん、僕の天の邪鬼的性格によるやせ我慢、と言われればそれまでなんだけど──無意識のうちに、かつての美少女スター「操ちゃん」とクラスメート「小山内さん」を区別して考えていたせいかもしれない。 そして素顔のミミちゃんをある程度知ってしまった今では、たとえ誰に何と言われようと、自分の友達を「見せ物」にする気なんて毛頭ないんだ。
ひと泳ぎして砂浜の上で寝そべっている時、さっきの食事のことが話題になった。
「でもさ、ほんと驚いちゃったなあ、ミミちゃん達には」
僕は食事の時のミミちゃんと雪子さんの名演技を思い出していたんだ。
「何が?」
ミミちゃんは砂の上に寝そべって、気持ち良さそうに目をつむったまま尋ねた。 ショートカットの髪からしたたる水滴がキラキラと輝き、可愛い横顔を一層ひきたてている。
「息ピッタリだったもんねー。たいしたもんだよ、二人とも」
「けっこー付き合い長いからね、雪ちゃんとは」
「ミミちゃん、やっぱり慣れてるんだなあ、あーゆーこと。
僕なんか緊張しちゃって汗だくだったよ」
「そーでもなかったわよ、なかなか良くやってたじゃない。
あたしはちょっぴり失敗しちゃったけどね」
「失敗って、何が?」
「ほんとゆーと、清純可憐な操ちゃん役やろーとしてたんだけどね、あったまきて、地を出しちゃったんだ」
「頭きたって?」
「あの、『タダシ』だか『ワルシ』だかって人よ。
ほんっと、あったまくるったらないなー」
その時のことを思い出したのか、ようやく開いたミミちゃんの目には怒りの色があった。
「確かに、気に入らん奴だけどね。
やたら馴々しく『操ちゃん、操ちゃん』なんて話しかけてたし」
「あたしはいーのよ。
あたしは馴々しくされたり、色々言われるの慣れてるから。
でも、伴ちゃんをあんなイヤラシー目で見て、あんなひどいことゆーんだもんねー。
ムカッときて、つい皮肉言っちゃったのよね」
「僕、そんな変なこと、言われたかなあ……」
と、当の伴ちゃんは相変らず呑気なもんだ。
「言われたわよー、覚えてないの? ほら、アイツが二枚目ぶって、森田健一に似てるから、モテたとか何とか言ってたでしょー?」
ミミちゃんにそう言われても伴ちゃんはピンと来ないらしく、曖昧に微笑んでいるだけなので僕が代わりに答えてやった。
「うん、うん、僕も覚えてるぜ、伴ちゃん。
それであの野郎、伴ちゃんのこと、挑発するような目で見てたなあ」
「それよ、そん時よ!
でもって、『男は外見じゃない』とか、『ハンサムには飽きたんだろう』とか、アイツ、伴ちゃんのこと、まるで、まるで……」
ミミちゃんはその先を言いよどんでしまった。 僕にはその先の言葉がおおよそ見当ついたし、彼女が言いよどんだ気持ちもよく理解できたので、今度はミミちゃんの代りに続けてやった。
「ひどい顔だってバカにしてたのさ、彼。
何でこんなのが、ミミちゃんのボーイフレンドなんだろうってね」
「そんな、何も、あたしはそんなつもりじゃあ……」
ミミちゃんは赤くなって、非難するような目で僕を見た。 大丈夫だよミミちゃん、伴ちゃんはそんな些細なこと気にするような、小さな人間じゃないんだ。
「そうだっけねえ。僕、あんまり覚えてないんだよ、あそこで話してたこと」
伴ちゃんは、邪心のない人懐っこい笑みを浮かべた。
「でも、小山内さんっていい人だから、まわりのみんなを、いい気持ちにさせるってとこあるよね。
みんな、小山内さん見て、嬉しそうだったもんね」
「そ、それは誤解よ、伴ちゃん!」
ミミちゃんはあせったように体を起こし、もどかしげに手を振りながら、
「みんなが嬉しそーにしてたのは、あたしのせーじゃなくって、どー言ったらいーんかなあ、あたしがヘンな仕事してたせーなのよ」
「変な仕事?」
「なんつーか、珍しーからなのね。
ちょうどパンダやコアラみたいに、物珍しーもんだから、見たってだけでみんな喜んじゃうわけよねー」
「そんなことないよ。
小山内さんって純真だから、まわりのみんなを、きれいな気持ちにさせるんだよね。
だから、あの正って人も、子供みたいに喜んで、はしゃぎすぎたんだと思うなあ。
悪気があったわけじゃないんだよ、きっと」
「違うわ、伴ちゃん、それは違うわ、あたしはそんな……」
つぶやくようなミミちゃんの声は、そのまま途切れてしまった。
いつものことだけど、人の良い面ばかりを見ようとする、いかにも伴ちゃんらしい言葉だった。 伴ちゃんは、どんな人でもどこかしら良い所を見つけ出して誉めようとするんだ。 それが誠実な本心からのものだから、お世辞でもイヤミでもなく、文字通りの誉め言葉として素直に受け取ることができてしまう。 でも伴ちゃんが見つけ出す他人の良い所は、伴ちゃん自身のきれいな心の反射に他ならず、結局その誉め言葉は、誉められた人よりも、むしろ誉めている伴ちゃんという人間をより強く反映することになるんだ。 他人という鏡を通して自分自身を眺めていて、しかもそのことをまるで意識していない伴ちゃんにとって、周囲の人間はみんなきれいな心の持ち主ばかりに思えるんだろう。
「だから、悪く思わないであげなよ、小山内さん」
どうしたわけか、ミミちゃんは伴ちゃんから目をそらして海の方を向き、可愛い横顔を見せたまま返事をしなかった。
「小山内さん……? まだ怒ってんの、小山内さん?」
「あたし、ちゃんと呼んでくれなきゃ、返事しないことにしたのよね」
「え?」
いきなり話題が変わったので、伴ちゃんは戸惑った表情でミミちゃんの横顔を覗き込んだ。
と、急にミミちゃんが振り向き、じっと伴ちゃんの顔を見つめながら、
「さっきから聞いてれば、何よ、『小山内さん』、『小山内さん』って。 食事の前にちゃんと練習したでしょー?」
ミミちゃんの怒ったような態度は一種の照れ隠しだったんだろう、言葉つきは怒ったようでも、どこかすねたような甘えた響きがあった。
「で、でも、ここには、僕等しかいないんだし……」
「何言ってんのよ、今日初めて会った人だって、あたしのこと『操ちゃん』なんて馴れ馴れしく呼んでたじゃない。
……それとも、あたしはまだ友達じゃないってわけ?」
「と、とんでもない!
ごめんね、僕、今まで、女の子の友達、あんまりいなかったもんで……。
ごめんね、ミミちゃん」
「そー、そー、そーゆーふうに、素直に呼んでくれたらいーのよねー」
突然、ミミちゃんは伴ちゃんの手を取って立ち上がった。
「も1回泳ご、伴ちゃん!」
「う、うん、そりゃあいいけど……」
「行こっ!」
あっけにとられている僕と雪子さんを残し、ミミちゃんは面食らう伴ちゃんを引っぱって、波に向かってかけて行ってしまった。