
 3へ
3へ
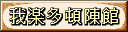
 webmaster@snap-tck.com
Copyleft (C) 2000 SNAP(Sugimoto Norio Art Production)
webmaster@snap-tck.com
Copyleft (C) 2000 SNAP(Sugimoto Norio Art Production)
「……そうですか、雪子さんの高校時代の友達なんですか」
例の正氏がニヤニヤしながらミミちゃんに言った。 彼はさっきからミミちゃんにばっかり話しかけ、雪子さんなんてまるで無視してしまっている。 今、大学の四年生で、笹岡家の次男だから、ゆくゆくは笹岡自動車工業の重要なポストに座らなきゃならないんで困っているんですよ、 などと言いながら、図々しくも自分の価値をミミちゃんに印象付けようと躍起になっていた。
「ええ、雪ちゃんと同じクラブで、一年後輩だったんです」
さすがにミミちゃんはこういった場は慣れっこになっているのか、一向に臆した様子もなくニコニコと愛想良く質問に答えている。 その清純そうな表情は素顔のお茶目な大学生「小山内ミミ」というよりも、かつての美少女スター「南井操」を髣髴とさせた。
「クラブは、何をやってたんですか?」
「テニス部です」
「テニス部ですか、それは、それは……」
なーにが「それは、それは」だ!
彼には、一度も会ってないうちからこっちの都合だけで勝手に悪い印象を抱いてしまっていたけど、実際にこうして会ってみて、その印象は拭い去られるどころかますます悪化の一途をたどっている。 僕の見たところじゃあ、彼はお金持ちのドラ息子であるだけでなく、道楽者のプレイボーイでもあるようだ。
「テニスなんて、ハイセンスでいい趣味ですねぇ。
僕も少しやっていたことがあるんですがね、ここにはテニスコートもあるようですし、どうです、後でひとつ、お手合わせしてもらえませんか?」
「残念ですけど、あたしは仕事で必要だったからやってただけで、恥ずかしいくらいヘタクソですし、それにもう辞めちゃったもんですから……」
「そう言えば、操ちゃんはテニス部のコの役が多かったですねー。
ほら、あれ、何でしたっけ、森田健一が剣道部か何かで、操ちゃんがテニス部のやつ……」
「『オレは青春だ!』ですか?」
「そー、そー、それ、それっ!
あの時のあなたは本当に可愛かった、清純そのものって感じでしたねえー。
僕も、せっせとあなたのブロマイドを集めたもんでしたよ」
「ありがとうございます。
昔のマネージャーが聞いたら喜びますよ」
今日会ったばかりだってのに、もう馴々しく「操ちゃん」なんて呼びやがって、どう考えても気に入らん奴だ。 僕だって、さっき初めて「ミミちゃん」って呼んだばかりなんだぞ!
ミミちゃんもミミちゃんだ、いきなり「操ちゃん」なんて、大学でそう呼ばれてもたいてい知らんフリしている名前で呼ばれたのに、ニコニコと愛想良く相手になっているなんて……。 そんな彼女を見ていたら、何だか無性に腹が立ってきてしょうがなかった。 もちろんこれは僕のひがみ根性のなせるシットで、ミミちゃんにしてみれば、いわば通りすがりの相手に対して、「あたしはもう南井操じゃなくて小山内ミミです!」なんて、いちいち断りを入れるのも面倒なんだろう。
「僕もねえ、これでも昔は森田健一に似ていると言われて、けっこう女のコにモテたこともあるんですよ」
と言いながら、彼の目は挑発するように伴ちゃんに注がれていた。
確かに彼は背が高く、どちらかと言えばハンサムの部類に入るし、高級そうなハデっぽい服を着て、一見してすぐ金持ちとわかる格好をしているから女の子にはモテるんだろう。 彼と伴ちゃんを比べたら、まさに月とスッポン、100人中99人の女の子は彼を選ぶだろうけど、外見に惑わされず中身まで見抜くことのできるような、 そんな人を見る目を持った女の子だって、ひとりくらいはいるんだぞ──いや「いて欲しい」という僕の願望でもあるんだけどね、正直言って。
男としての僕の目から見た彼は、やたらとキザッたらしさばかりが鼻につく上、うぬぼれが服を着て歩いているような感じもあり、ひがみも手伝って全く気に入らないところだらけだ。
「そうですか、それは、それは……。 あたしは、あの人、あんまり好きなタイプじゃないんですけど、まあ、人それぞれですから」
ミミちゃんの口調は穏やかで、相変らずニコニコとして愛想が良かったけど、どことなく皮肉の匂いが感じられる言い方だ。 僕は内心ニンマリとし、それとなく正氏の顔色をうかがってみた。 彼は今の言葉を皮肉と受け取ろうか、それとも他意のない素直な言葉と受け取ろうかと迷っている様子だったけど、いい方に解釈したらしく、すぐに気を取り直してわざとらしく驚いたような表情を作った。
「ほおー、じゃあ、操ちゃんの好みのタイプは、どんなタイプなんです?
やっぱり、そちらのボーイフレンド君のような……ですか?」
「もちろん、そのとおりです」
ミミちゃんは至極当然といった表情で、伴ちゃんに優しい微笑みを投げかけた。
でかしたぜ、ミミちゃん! ミミちゃんはそんじょそこらのミーハーとはわけが違うんだ、お生憎様、プレイボーイ君。
ところが肝腎の伴ちゃんときたら、ミミちゃんに微笑みかけられたってのに、ポカーンとした表情で彼女の方をぼんやり見返しているばかりなんだ。 どうもミミちゃんのボーイフレンド役という自覚がほとんどないようで、現在話題の中心になっているのは他ならぬ自分のことなんだという事態を、十分把握し切っていない顔つきだ。
「……なーるほど、さすがは操ちゃん、男は外見じゃないってわけですか。
やっぱり芸能界にいた人は違いますねえ、ハンサムは周囲にゴロゴロしていたもんで、見飽きてしまったってわけですね?」
「いーえ、外見ですよ。
芸能界には、ほんとーにいい顔の男の人なんていやしませんから。
やたらとうぬぼれてて、キザッたらしくて、カッコウばっかりで、まるで風船玉みたいに中身がカラッポなんですよね」
「ヘェー、そ、そんなもんですかねえ……」
さすがの正先生も、今度は間違いなく皮肉を言われたことに気づいて、話を続ける意欲をそがれてしまったようだった。
これを見ていた雪子さんの父の耕平氏が、その場を取り繕うように口を開いた。
「そういえば、雪子のボーイフレンド、荻須君だったっけ、彼に会うのは初めてだな、雪子」
耕平氏は50がらみの痩せて小柄な人物だけど、眉間に気難しそうなしわを寄せ、頑固一徹といった感じの眼差しが、さすがに人を威圧するだけの力を持っている。
雪子さんは何食わぬ顔で、白々しい笑顔(と、事情を知っている僕には思えたんだ)を父親に向け、
「あら、お父さん、友規君と会うの初めてだったかしら?」
「やっぱり、お前も外見で選んだのか?」
「もちろんよ。
あたし、ミミちゃんと好みのタイプが似ているもんだから、いつも奪い合いになってしまうのよ。
……ね、ミミちゃん?」
と、雪子さんはミミちゃんに意味ありげな視線を送った。 ミミちゃんも心得たもんで、すぐに雪子さんに調子を合わせた。
「そーね。
でもって、たいてーあたしのほーが勝っちゃって、ハンサムを奪っちゃうのよねー」
「そー言えば、そーだったわねえ。
でも、今度はうまく別々のコになったから、良かったじゃない?」
「まーね。
そんでも、やっぱ、あたしの方がハンサム選んだと思うなー」
「まあ、ミミちゃんったら……。
けっこういい勝負よ、どちらも」
全く、二人共たいした役者やのう! ほとんど打ち合わせもしてないのに、息がピッタリだ。 僕は、自分のことを言われているにもかかわらず、恥ずかしがるのも忘れて二人のやりとりを感心して眺めていた。
「どこで知り合ったんだ、一体?」
耕平氏、そう言いながら、僕の方にうさん臭げな視線をチラチラ送っている。 いかん、いかん、ここでボロを出したら、せっかくのミミちゃん達の名演技が元も子もなくなってしまう。 僕は頭をかいて、恥ずかしがってるような表情を作った……と自分では思う。
「ミミちゃんと同じ大学で、同じ学部なのよ。
前にミミちゃんの大学に遊びに行ったことがあって、その時紹介されたの」
「大学はどこなんだ?」
「東横大学の理学部よ」
「東横大学?
フーン、そうか、一応、国立なんだな、二流だが。
……だいたい、理学部ってのは何をするとこなんだ、ええ?」
どうも耕平氏は何とか僕のアラを捜して、娘のボーイフレンドにはもったいないってことを認めさせたいらしい。 なんの、ここで気後れしていては僕の役目が果せない。 僕はできる限りにこやかな顔をして、耕平氏と雪子さんの会話に割り込んだ。
「理学部とゆーのはですね、一口に言えば、科学者の卵を育てる所なんですよ、持田さん」
「科学者の卵? 商売柄、わしも少しは科学者を知っとるが、あんな頭の堅い連中はどうもならん」
「は!?
は、はあ……」
いきなり先制パンチを食らってしまって、我ながら情けない返事だ。
「自分の興味だけで研究しおって、社会への貢献ってことをまるで考えておらん。
どうしようもないエゴイストどもだ」
「はあ、そ、そうかもしれませんね……」
「うちの開発の連中にもいつも言っとるんだ、採算性を考えて、モトの取れるようなモノを開発しろってな」
「はあ、そうですか……」
「だいたい企業ってもんは、利益をあげて存続してこそ意味があるんであって、それでこそ社会に何らかの貢献をすることができるんだ。
つぶれちまっては元も子もあったもんじゃない」
耕平氏、完全に社員に訓示を垂れている調子だ。 自分で働いたこともなく、社会もほとんど知らない親のスネッかじりとしては、この手の話題には全く太刀打ちできない。
「だから、企業の使命は利潤追及にあるのであって、これは恥じることじゃあない。
それを何にも知らん科学者どもが、やれ公害だ、やれ企業のエゴだなどと言って、マスコミを煽りたてるからいかん」
「まあ、まあ、食事の時に仕事の話はヤボってもんですよ、持田さん」
と言ってとりなしたのは、正さんの父、笹岡良介氏だった。 彼は恰幅の良い白髪の中年で、どことなくカバを思わせるような人物だけど、カバみたいにお人好しなところは微塵もなく、いつも人にペコペコされている人特有の、尊大で傲慢な態度がやたらと目につく。
「それに、そんな難しい大人の話をしたところで、その子達にはまだ理解できないんじゃないですかな? そういう話がなるほどと納得できるのは、世間の荒波にもまれて、人間ができてからですよ」
良介氏は、いかにも鷹揚な口調でにこやかに言った。 でもそのにこやかな笑顔の下から、僕等のことをまるっきり子供扱いしていて、バカにし切っていることがアリアリと透いて見えるんだ。
そりゃあ確かに僕等若者は、世間の苦労も知らず、大学という温室の中でヌクヌクと暮しているけど、それだけに世間ずれしていない曇りのない目で物事を見つめ、何者にも縛られない自由な環境で、自分なりの価値観を築き上げることができるんだと思う。 人からの押し付けでもなければ受け売りでもない自分なりの独自な価値観を、世間体や損得勘定でがんじがらめになった社会から一歩離れて、じっくりと築き上げることができる場所と時期といったら、大学時代をおいて他には少ないんじゃないだろうか。 これだけでも僕は大学に入って良かったと思っているし、少なくとも僕に関する限り、大学の本当の目的はそんなところにあるんだという気がしてならない。 僕はまだそんなに確固とした価値観を持っているわけじゃないけど、汚れのない目で物事を見極めたいという気持ちだけは、ずっといつまでも持ち続けていきたいと思っているんだ。
「それは、そうかもしれませんな。
今時の若いもんときたら、親の苦労も知らんで、大学で一体何をしとることやら。
おおかた、親が苦労してかせいだ金を、下らん遊びに使ってしまっとるんでしょうなあ……」
「嫌だわ、お父さんったら!
友規君もあたしも大学でちゃんと勉強して、それなりに真剣なのよ、そんな失礼なこと言わないで欲しいわ」
防戦一方で手も足も出ない僕に代わって、雪子さんが矢面に立ってくれた。
「何を一人前なことを言っとるか。
だいたい女ってもんは、結局は結婚して家庭を守るのが勤めなんだし、それが一番幸せなんだ。
だから、わざわざ親元を離れて下宿なんぞせずに、家で花嫁修行でもしておればいいものを、それを……」
「また、そんなァ……。
言っておきますけどね、あたしはまだ、結婚なんてこと考えたこともありませんからね」
「まあまあ、何ですか二人とも、お客様に失礼じゃありませんか」
雪子さんの母親の静さんがたしなめるような口調で二人のやりとりをさえぎり、僕の方を向いて申しわけなさそうに続けた。
「すみませんねえ、荻須さん。二人共、わがままなもんですから……」
「いえいえ、大事な娘さんのことですから、当然だと思いますよ」
「そうですかねえ。
娘の気持ちも、よく理解してやればいいんですけどねえ……」
静さんが、本当にもうこの人は……とでも言いたげな目を夫に向けると、耕平氏はそんな視線の非難に躍起になって答えた。
「お前が、そうやって甘やかすからいかん。
だいたい、雪子が下宿して大学に通いたいなぞと言い出した時も、わしは反対だったのに、お前が……」
「何を言ってるんですか、会社じゃあ『これからは女性の時代だ』なんて進歩的なことを言っているくせに、自分の娘のこととなるとすっかり封建主義なんですから」
「そ、そんなことはない!
ただわしは、雪子にはちゃんとした、しかるべき相手を探してやりたいんで、親元を離れて、わけのわからん男にひっかかってもいかんと思っとるだけなんだ」
「大丈夫ですよ、雪子は、これでも人を見る目は確かなんですから」
と言いながら、今度は雪子さんに向けた静さんの目は優しげに微笑んでいた。
「ただ、今の若い人は、昔のように家柄だとか何だとかいった、古臭いものにとらわれていないだけなんですよ」
雪子さんは、どうやらこの母親の血を濃く引いたようだ。 そう思ってよく見ると、上品な顔立ちといい、優しげな目元といい、なるほど二人はすぐに母娘とわかる似通った雰囲気を持っている。
「あたしだってねえ、これでも昔は、ロマンチックな恋に憧れたもんでしたよ。 慣習だらけの古臭い家から連れ出してくれる、素敵な人が現れないものかと、そんなふうに夢見ていたことだってあったんですよ」
静さんは夢見る少女のような目をして、上品に笑った。
「で、それがお父さんだったってわけ?」
雪子さんが、信じられないという視線を父親に投げつけながら聞いた。
「とんでもありませんよ。 結局、夢は夢だけで終ってしまって、親同士が決めた相手と一緒になったんですよ。 そういう時代だったんですよ、あの頃は……」
ここで、昔を懐しむような色をしていた静さんの目が、急にいたずらっぽくキラッと輝いた。
「でもね、これでこの人にも、けっこういいとこがあってね。 結婚式の前の日に、二人だけになった時にね……」
そこまで話して、静さんは急にクスクスと思い出し笑いをし、話をとぎらせてしまった。 まるで少女のように気持ちの良い笑いだ。 そんな母親の態度にしびれをきらしたのか、雪子さんがじれったそうに言った。
「ねえ、ねえ、それからどうしたの? 二人だけになってどうしたのよー」
「この人ったらね、親が用意してくれた高価な結婚指輪と一緒に、自分で買った安物の結婚指輪を出して、『もし良かったら、結婚式ではこっちの指輪をはめて欲しい』って言ったのよ」
「安物の指輪を?
どうしてまた、そんな……?」
「その頃のこの人には、それが精いっぱいの買い物だったんですよ。
親同士が決めた結婚だけど、自分も決して嫌がってるわけじゃない、この結婚は自分の意志でもあるってことを、それで伝えたかったらしいのよね」
「ヘェーッ、信じられない! まさか、お父さんがそんな……」
「よさんか、そんな古い話を今更……、お客様の前だぞ」
などと言いながら、耕平氏はくすぐったいような、そのくせ満更でもないような表情だった。
意外の感に打たれたのは雪子さんだけじゃなかったようだ、まわりのみんなの口からも、声にならない驚きのため息がもれている。 おかげでその場の雰囲気がいっぺんに和やかなものとなり、話題が僕等から離れてしまった。