
 6へ
6へ
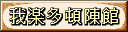
 webmaster@snap-tck.com
Copyleft (C) 2000 SNAP(Sugimoto Norio Art Production)
webmaster@snap-tck.com
Copyleft (C) 2000 SNAP(Sugimoto Norio Art Production)
二人はしばらく無言で青年が出て行ったドアを眺めていたが、やがてトモヒトがほうっとため息をついて、ドアを眺めたまま、ぼんやりと独り言のようにつぶやいた。
「時間が遅くなり、空間が縮む、か。
信じられない話だなあ……」
「そうね。
でも、1つだけ確かなことがあるわよ」
ミミの口調はトモヒトと違ってきっぱりとしていた。
「確かなこと……?」
トモヒトが振り向くと、ミミはまだドアから眼を離さずに、
「そ、確かなこと。 あの人、トモヒトとおんなし種類の人間で、あの人の話すことは、全部自分の頭で考えて、全部自信持ってることばっかだってこと」
それからクルッと向き直り、真顔でトモヒトをじっと見つめた。
「あたし信じるわ、あの人が言ったこと。 理屈はよくわかんないけど、とにかく信じちゃう!」
まるで非難に答えるかのようなミミの強い調子に、トモヒトは慌てて弁解するように、
「う、うん、僕だって信じるよ、もちろん」
と答えたが、ふと思いついて、
「……そういえば、あの人、何て人なんだろ?
ミミ、知らない?」
「あっきれたァ!
相手の名前も知らないで話してたのォ!?
ほら、入会ん時に自己紹介してたじゃない、相変わらず物覚え悪いわねェ」
申し訳なさそうに肯くトモヒトに、ミミはやれやれといった視線を投げかけながら、
「あの人はアルベルト、アルベルト・アインシュタインって名前よ」
「アルベルト・アインシュタインか……。
不思議な人だね、ほんとに……」
二人は肯き合って、どちらともなく青年が出て行ったドアに再び目をやった。
二十世紀も明けそめたある冬の夜、雪深いスイスの街の片隅で、物理学の革命が静かに始まろうとしていた。