
 2へ
2へ
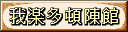
 webmaster@snap-tck.com
Copyleft (C) 2000 SNAP(Sugimoto Norio Art Production)
webmaster@snap-tck.com
Copyleft (C) 2000 SNAP(Sugimoto Norio Art Production)
敬虔な余韻を部屋に残して、弦楽の響きが静かに消えた。 演奏者達は、落日の温もりを楽しむ木の葉のように、快い余韻に身を任せたまましばらく動こうとしなかった。
市民音楽愛好クラブの練習場になっているその部屋には、いつものように雑多な人間がつどっていた──ビオラを手に、椅子にめり込むように腰掛けている、白髭をたくわえた小柄な老人、チェロを抱えてどっしりと陣取っている、髪の少し寂しくなった中年の男、バイオリンを持って仲良く並び、視線を交わし合っている若い男女──歳も職業も様々ながら、どの顔にも音楽という共通の趣味を持つ者の心暖まる安らかさがある。 窓の外にはひっそりとした冬の夜があった。 無数の星を散りばめた空に、葉をすっかり落とした街路樹の影が濃い。 夜の底は深い雪でぼんやりとほの明るく、それが、むしろほっと暖かいもののように感じられるのは、赤々と灯された暖炉のせいばかりでなく、部屋に溢れた快い余韻のせい、心のせいでもあったろう。
やがて前で指揮をしていた男が散会の挨拶をすると、明るいざわめきが広がり、そこここに談笑の輪ができた。 練習を終え、取り留めのない会話を楽しむひとときが、これまた世の喧騒から離れた静かな憩いだった。
「やっぱりいいなぁ、バッハは。 なんか、心が洗われるような気がするよ」
バイオリンを片付けながら、学生風の男がしみじみとした口調で言った。 外見には無頓着なのか、薄汚れた服装でボサボサの髪をしているが、透き通った小さな瞳と、どことなく幼さを残した表情が、小柄な体と相まって、少年のように人懐っこい雰囲気を漂わせている。
「心が洗われるって、もうそんなに汚れちゃってるわけ、トモヒトの心は?」
からかうような親しみのこもった声は、隣のやはり学生風の女だった。 黒目がちの大きな目がいたずらっぽい光に輝き、それでいて、くるむような優しさをたたえて相手を見つめている。 大きな目に比べ不自然なほど小ぢんまりした鼻と、楽しげな微笑みを匂わせた口元が、卵型の顔に程良く包まれ、髪を思い切ったショートカットにしているせいもあってか、 顔全体から受ける印象はどこかしらあどけなく、美人というよりも、女を意識させない幼女めいた愛くるしさがあった。
「何言ってんだよ、ミミ。 汚れてなくたって洗われるんだよ、バッハは」
トモヒトと呼ばれた若者は生真面目な様子で答え、部屋の窓に視線を送った。
「何となく、『十億光年の沈黙』って感じがしない?」
明るい部屋に、窓は夜空を四角く切り取って黒々と深く、そこだけ別次元のようにどこまでも視線を吸い込んでいきそうだった。
「十億光年の沈黙……?
なんかえらく哲学的ね、今夜は。どうかしたの?」
「別にどうもしやしないけど、バッハを演奏してると、何てったらいいか、こう、無限の静寂って感じで……」
トモヒトは自分の感覚をうまく言い表せないのか、もどかしげに手を振って黒い窓を示し、
「ほら、ちょうど星空を見上げた時のようにね、まるで自分が宇宙に浮かんでるみたいでさあ……」
「何が『無限の静寂』よ、柄にもなくロマンチックなセリフ!」
からかうようにそう言いながら、トモヒトの身振りにつられて窓を見たミミは、夜空に茶目っぽさを吸い取られたように、フッと遠くを見つめる目色になった。
「無限の静寂ねェ……。
可愛い彼女には、ロマンチックな言葉ひとつかけられないくせに、音楽や科学の話になると、俄然ボキャブラリィ豊富になっちゃうんだから、トモヒトは」
「そ、そんなことないよ、ぼ、僕だって、いざとなったら、そりゃあ、音楽や科学は好きだけど、それとこれとは話が別で……」
ミミの言葉を生真面目に受け取って、トモヒトがしどろもどろになっていると、
「おや、トモヒト君も科学に興味を持っているんですか? それは嬉しいですね、実は僕もなんですよ」
と、隣でバイオリンの手入れをしていた青年がにっこりと振り向いた。 それはつい1週間ほど前に新しく入会した青年で、人の名前を覚えるのが苦手なトモヒトは、その青年の名前を思い出せず、
「そ、そうですか……」
と口ごもったまま、言葉を待つように相手を見た。
青年はすでに社会人らしく、一応それなりの格好をしているが、お世辞にもセンスが良いとは言えない服装で、髪を無造作に長くのばし、不揃いな口髭をたくわえている。 しかし、彼の印象をむさ苦しさから救っているのは、控え目な暖かい笑顔と、不思議な輝きを帯びた目だった。 瞳の中に別の生命を宿しているように生き生きと輝くその目は、どこまでもどこまでも哀しいほどに澄み切っていて、さわやかなユーモアと共に、一抹のペーソスすら感じさせる不思議な魅力を持っていた。
トモヒトは青年の目を見た途端に、ほのぼのとした暖かみが胸にしみて、それはその青年に肉親のような親しさを覚えたのだった。 それほど歳は違わないと思われるのに、まるで父親のようにホッとする大きな暖かさだった。
「トモヒトはね、科学のこととなると、夢中になっちゃうんですよォ」
ミミが、まるでトモヒトの母親然とした表情で、
「こないだなんて、鏡見ながら真剣に悩んでるもんで、『とうとう、自分のひどい顔自覚したの?』って聞いたら、何て答えたと思います?」
「さあ……、何と答えました?」
ミミの口調は、トモヒトをけなしているというよりも、誉めているような朗らかさだったので、相手の青年の表情にも穏やかな笑みがあった。
「『もし光より速く走りながら鏡を見たら、自分の顔が写るもんかなあって考えてたんだよ』ですって!」
ミミは、どうです呆れちゃうでしょう、と言いたげな表情でトモヒトを見やったが、青年は驚きも呆れもせず、穏やかな表情のまま、むしろ興味深げにトモヒトを眺めて、
「ほほう、君もそんな疑問を……?
実を言いますと、僕も同じ疑問を持ったことがあったんですよ」
「えっ、あなたも!?
そうですか、あなたもですか、やっぱり……」
青年の瞳の奥に改めてそれと納得するものを認めて、トモヒトは何となく嬉しくなった。 親しいと感じ、暖かいと感じたのは、青年が自分と同じ種類の人間だからだろう。
「へェー、あっきれたァ! 世の中には、トモヒトみたいにおっかしなこと考える人が、他にもいるのねェ!」
叫ぶようにそう言ったミミの声にも表情にも、やはり相手をけなすようなところはなく、トモヒトの仲間を見つけたという素直な驚きと喜びが溢れていた。 そしてそれは、トモヒトに対する彼女の感情を無邪気に反映していて、青年に新たな微笑みを浮かべさせた。
「そういった、子供のように純粋な好奇心が、科学にとって一番大切なんですよ、ミミさん」
青年は微笑みをミミからトモヒトへと移し、
「それでどうなりました、その疑問の答は?」
青年もトモヒトの中に自分と似たものを見たのだろうか、表情も態度もさほど変わらないのに、体全体から古い友人のような懐かしい親しさが漂い出してきた。
「それが、残念ながら結局わからずじまいで、今だにまだ悩んでるんです。
例の、マイケルソンとモーレーの実験結果もあることですし……」
「ははぁ、やっぱり君も、あの実験結果に興味を持っているんですね?」
「何、そのマイケルソンとモーレーの実験って?」
二人の顔に交互に視線を移していたミミが、怪訝な表情でトモヒトに尋ねた。
「マイケルソンとモーレーって人が、光に関する有名な実験をやっててね。
それが、僕にはちょっと理解できない、不思議な結果なんだよ」
「不思議な結果って?」
「彼等の実験によるとね、光というものは、光源や観察者がどんな運動をしてても、常に一定の速度を持つ、ということなんだよ」
トモヒトの言葉が理解できないのか、ミミはちょっとの間ポカンとしていた。
「……どういうこと、それ?
ねえ、あたしみたいな普通の人間にもわかるように、もっとわかりやすく説明してよ」
「つまりね、例えば走ってる列車から石を投げたとするよ。
そうすると、その石の速さは、列車に乗ってる人から見た場合と、地面に立ってる人から見た場合とでは、違って見えるはずだよね?」
「そりゃそうよ。
もし列車の進んでる方向に投げたとしたら、列車のスピードがプラスされちゃうから、地面に立っている人から見れば、当然、もっとずっと速く見えちゃうし、もし列車と反対方向に投げたとしたら、逆に、もっとずっと遅く見えちゃうはずよね」
「だろ?
ところが、石を投げる代わりに、マッチをすって光を出したとしたら、その光の速さはそうならずに、列車に乗ってる人が見ても、地面に立ってる人が見ても、どっちも同じだったってことなんだよ!」