
 第7章へ
第7章へ
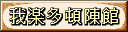
 webmaster@snap-tck.com
Copyleft (C) 2000 SNAP(Sugimoto Norio Art Production)
webmaster@snap-tck.com
Copyleft (C) 2000 SNAP(Sugimoto Norio Art Production)
「いやー、無事お茶が飲めて良かったねー、伴ちゃん」
「ほんと、ほんと。
友則があんなこと言い出すもんで、一時はどうなることかとあせっちゃったけどね」
「僕だって、清水の舞台から飛び降りたつもりでミミちゃんに任せたんだぜ。
それがさー、こーして何事も無くお茶が飲めるなんて、上手くいきすぎて怖いくらいだよ、実際」
奇跡的と言おうか、天変地異の前触れと言おうか、ミミちゃんが何ひとつ壊すことなくお茶を入れ終え、僕等はしばしの休憩を取っていた。
「なんか、あたしがまともにお茶入れると、革命でも起きそーな口振りねー、二人とも」
僕と伴ちゃんの会話を聞きとがめて、ミミちゃんはふくれっ面をしながら言った。
「いやいや、とんでもない。
伴ちゃんのために、一生懸命努力しているミミちゃんの姿は非常に美しい。
きっと神も感動して、奇蹟を起こしたもうたのであろう。
信じるものは救われる、アーメン……」
「天にまします我等が主よ、二匹の狼に囲まれた迷える小羊をお救いください、ナンマイダブ、ナンマイダブ……」
と、ミミちゃんも調子を合わせた。
「それじゃあ、お祈りも済んだことだし、そろそろ続きを始めようか?」
伴ちゃんが、片田舎の牧師のようにのどかな口調で言った。
「もー始めちゃうのォ?
せっかく人が清らかな気持ちになってるとこなのに、邪悪な話で汚そーってわけ?」
「邪悪な話ってねぇ、語学の話よりは清らかだと思うけど……」
「あら、それは伴ちゃんの偏見よォ。
語学差別ハンターイ!
我等に自由を!
光を、もっと光をーっ!」
「そんなに薄暗いかなぁ、この部屋……?」と、伴ちゃんは四畳半中を見回し、「確か、大家さんとこに懐中電灯があったから、借りて来てあげようか?」
「何とゆー教養の無さ!
彼女として恥ずかしーわ、あたし。
ゲーテの有名な最後の言葉よ、これは」
「ゲーテって、あの、佐藤スケトラだかって人が、何かしたとか、言ったとかって本を書いた人?」
「佐藤スケトラ……?
もしかして、ツァラトゥストラじゃないの、それ?」
「あっ、そうそう、そんな感じの人」
「『ツァラトゥストラかく語りき』なら、ゲーテじゃなくてニーチェだぜ、伴ちゃん」と、僕が口を出した。
「そーよ、伴ちゃん。
ゲーテは、『to be or not to be, let it be !』って有名なセリフ言った人よ」
「あのねー、ミミちゃん、なんでハムレットがビートルズ歌わにゃならんのだよ!」と、僕はあきれて、「だいたい、ハムレットを書いたのはシェークスピアだぜー」
「あら、そーだっけ?
まあ、細かいことはどーだっていーのよ、この際。
伴ちゃんみたいに、佐藤って日本人と間違えたわけじゃないだけ、まだいーじゃない」
「五十歩五十一歩だよ、どっちも」
「それをゆーなら、五十歩百歩でしょ?」
「50歩も差は無いさ。せーぜー1歩ってとこだね、伴ちゃんとミミちゃんは」
「まー、失礼な!
あたしは友則君と違って足長いから、1歩でも、差はけっこーおっきいのよねー」
「なんと!
我がクラスの足長おじさんと呼ばれる、この私をつかまえて……」
「足の、指が長いの?
それとも、爪?」
「オランウータンか、わしは!?」
「あのー……」と、伴ちゃんが申し訳なさそうに口を出し、「そろそろ、統計学の話、始めちゃっていいかなぁ……?」
「いーとも、いーとも!」
「許す、許す、良きにはからってたもれ」
僕とミミちゃんが横柄にそう答えると、伴ちゃんは嬉しそうにニッコリして話し始めた。
「ありがと。
……さてと、えーと、そもそも推測統計学では、標本集団の要約値、つまり統計量から、母集団の要約値、つまり母数を確率的に推測するわけなんだけど、その方法には大きく分けて2つの種類があるんだよ」
「とゆーと、何と何?」と、ミミちゃん。
「1つは、母数が実質科学的に意味のある値と等しいか、等しくないかを調べる『検定』で、これは、リトマス試験みたいな定性試験に相当するんだよ。
もう1つは、母数がどれくらいの値なのかを推測する『推定』で、これはpH計みたいな定量試験に相当するんだよ。
つまりね……」
と言って、伴ちゃんは次のような図を書いた。
| 統計学的推測─ | ┌検定 testing (定性試験) ┤ └推定 estimation (定量試験) |
「……という具合で、統計学的推測ってのは、この2つの柱からできているんだよね」
「ケンテイとスイテイ?
どっちも、何となく邪悪な響きのある言葉ねェ」
「邪悪な響きって、検定と推定のどこが邪悪なんだい?」と、僕はミミちゃんに尋ねた。
「だって、試験とかテストとかゆーたぐいのもんって、根っから肌合わないタチなのよねー、あたしって」
「誰だって、そんなもん肌合うわけないさ。
伴ちゃんだって、これだけ科学的知識抜群なのに、テストとなるとひどい時あるからね」と言って、僕は伴ちゃんを振り向き、「ほら、いつだったか、化学か何かのテストで0点取ったことあったろ、伴ちゃん?」
「あった、あった。
先生にものすごく怒られちゃったよ、あの時は」
「伴ちゃんが0点!?
しーんじられないわァ、どして?」と、ミミちゃんが目を丸くして伴ちゃんを見つめた。
「うん、有機化学のテストだったんだけど、テスト中にちょっとしたアイデアを思いついて、どうしても書いておきたかったもんだから、テスト用紙に書いちゃって、テストの答、全然書けなかったんだよ」
「それで0点ってわけェ?
一体、何思いついたの?」
「い、いや、その、そう大したことじゃないんだけど、特殊相対性理論のこと考えてたら、急に、マックスウェルの電気力学方程式は、ローレンツ変換不変式じゃないかなって思いついてね、それを証明していたんだよ」
「……今の、ひょっとして火星語?」
「そうじゃないよ、理論物理の話だよ。
テスト用紙を出したら、先生にね、『物理の答案としてなら満点だが、有機化学の答案としては0点だ』って怒られちゃって……」
「あったり前でしょ、そんなこと!
あたしだって、そんなメチャしないわよ」
「伴ちゃん、あの後、やたら落ち込んでたもんなー」と、僕。
「そうなんだよ。
物理の先生に聞いたら、もうずっと前にその事を証明した人がいて、そもそも相対論の始まりが、その事からなんだって。
せっかくいいアイデアだと思ったのに、自分の勉強不足がわかっただけで、我ながら情けなくてねぇ」
「ダメだ、こりゃ。
反省の色がまるでない」
「そ、そんなことないよ、ものすごく反省したよ。
これからは、いくらいいアイデアでも、同じ事が前に発表されていないか、ちゃんと調べてみようって……」
「わかった、わかった、キミに常識を期待した、僕が悪かった」
「それで、2つの柱がどーしたっつーの、伴ちゃん?」と、珍しくミミちゃんが話を正道に戻す質問を発した。
「2つの柱……?
何、それ?」
「何って、統計学の話よ。
さっきの続きー」
「ああ、そうか、統計学の話だっけね。
えーと、2つの柱ね、2つの柱と……、何の話してたんだっけ、僕?」
「あっきれたァー、もー忘れちゃったのォ?
検定と推定の話だったじゃない。
先生がそんなことでどーすんのよ」
「あっ、そうそう、検定と推定だっけね。
そうだった、そうだった、ごめんね、ついよそ事考えてて……」
「しっかりしてよね、全く。
あーあ、やんなっちゃう!
ほんと、こんなことで将来大丈夫なのかしら?」
と、ミミちゃんはやれやれと言わんばかりに肩をすくめた。
「大丈夫ないよ、ミミちゃん。 悪いこと言わんから、今のうちに、将来性抜群の僕に乗り換えといた方がいーと思うよ」
と僕が言うと、ミミちゃんはおせっかいな猿でも見るような眼差しで僕を見て、
「ジョーダン!
大丈夫じゃないからこそ、あたしがついててあげなきゃいけないのよね。
友則君は、どっかそこらへんの、ウーパールーパーでも相手にしてなさいよ」
「ウーパールーパー!?
ウ〜〜、ウーパー、ウーパー、ルールー!」
「さ、伴ちゃん、友則君には勝手にウーパールーパーさせておいて、あたし達は真面目に統計学のお勉強しましょ」
と、またしてもミミちゃんが話を正道に戻した。
「うん、それじゃあ、まず検定から説明するとね、検定は定性試験で、言わば○×式だから、最初に必ず問題があるんだよ。 例えばさっきの体重の例で言えば、仮に50kgという値を標準体重と考えて……」
と言いながら、伴ちゃんはレポート用紙に次のように書いた。
「……という問題について調べてみることにするよ。
検定では、こういう具合に、実質科学的に意味のある基準値を設定して、母数がその値と等しいか等しくないかを問題にするんだよ」
「じゃ、実質科学的に意味のある基準値ってのは、どーやって決めるの?」
「それは統計学の守備範囲じゃなくて、統計学を利用する科学の守備範囲なんだよ。
例えば今の体重の例では、多分、医学か栄養学の専門家が、その分野の理論や知識に基づいて、しっかりと決めるべきものだよね」
「『餅は餅屋』って訳ね」
「そうだね。
それで、この問題に対する答えは2通りあって、日本人の平均体重、つまり母平均をμで表し、基準値50kgをμ0で表すと……」
と言って、伴ちゃんはまた次のように書いた。
「……と表現できるんだよ」
「またまた出たわね、わけのわかんない記号がどっさり!
さ、伴ちゃん、潔く説明してもらおーじゃないの、これ、一体どーゆー暗号?」
「暗号って、別にそんなんじゃないよ、これは。
H0はね、『帰無仮説』って言って、無に帰する仮説って意味だよ」
「無に帰する仮説?」
「うん。
普通、実験結果が基準値とぴったり一致するなんてことはほとんどなくて、H0は否定されちゃって、無に帰する仮説だから、そう呼ばれているんだよ」
「なるほど」
「それでH1はね、『対立仮説』って言って、帰無仮説と対立する仮説だから、そう呼ばれているんだよ」
「じゃ、この右側の式はどーゆー意味なの?
この鬼ボーフラみたいな記号は、どーゆー魂胆?」
「鬼ボーフラ……?
ひょっとして、δのこと?」
「そう、その統計脳炎を媒介しそーな、イヤラシイ害虫のことよ」
「これはギリシャ文字のデルタで、差を表す記号だよ。
母平均が基準値に等しいかどうかを調べるってことは、母平均と基準値との差をとって、その差が0かどうかを調べることと同じだから、こんなふうに表現することもあるんだよね」
「フーン、デルタだかカルタだか知んないけど、おかしな書き方ばっかすんのね、数学者って」
「まあね、確かに普通の書き方とはちょっと違っているけどね。
それで、この仮説のどっちが正しいか検定するために、日本人という母集団から標本集団を無作為抽出して、データを調べてみようってわけなんだよ」
「日本人全体から無作為抽出しようってのは、そりゃあ大変な作業だぜ、伴ちゃん」と、僕は注意を促した。
「そうなんだよ、実は。
だけど、最初に書いた問題を調べるためには、どうしてもそうしなくちゃならないんだよね」
「日本人全体から無作為抽出できなくて、集めやすい人ばっかり、適当に選んできた時はどーなるんだい?」
「本当言うと、そんな場合が多いんだよ。
そういう時にはね、その標本集団の背景因子から、結論を当てはめるべき準母集団を逆に規定するんだよ。
それから最初の問題や仮説を、『これこれという背景因子を持つ、準母集団の平均体重は……』という具合に、修正する必要があるんだよね」
「なーるほど、面倒くさいんだなぁ、統計学って」
「そうだね。でも、このことはものすごく重要なことなんだよ。
統計学に対する誤解ってのは、たいてい、このことをよくわかっていないのが原因なんだよね」
「じゃ、伴ちゃん、今回は特別に、日本人全体から無作為抽出できたってしてあげるから、次に進んでいーわよ」
と、またしてもミミちゃんが話を促した。
「ありがと。
……な、何か怖いなあ……」
「やっぱり伴ちゃんもそう思う?
実は、僕もなんだよ」
「あら、二人とも、何が怖いの?」と、ミミちゃん。
「だってさー、ミミちゃんがさー、さっきから、話を進めるよーな建設的なことばっかりゆーもんだから、何か薄気味悪くてさー」
「そうなんだよ、友則。
さっき、お茶を入れた時も、何にも壊さなかったよね?
やっぱり、どっか悪いんじゃないかなぁ……」
「それだけで済めばいーけど、何となく東海大地震でも起こりそーで、不気味だよ」
「フンだ、フンだ!
人が真面目に統計学してるのに、何さ、二人とも。
そーゆー周囲の不理解が、純真な青少年を非行に走らせるのよー」
「そりゃあ確かに、ミミちゃんの外見が少年みたいだってのは認めるけど、純真ってのはどーかなぁ?」と、僕。
「んっもー、失礼しちゃうわねー!
いーもん、もー知らないもんね、グレてやるんだもんねー」とミミちゃん、急にスケ番風な口調になり、「ちょっと、ちょっとォ、タバコちょーだいよォ、オジサン。
あたいと付き合わない?
いーとこ知ってんだからさァー」
「ほほう、なかなか板についておるのぉー。
じゃがな、お嬢さんや、もうあんたの年じゃあ、タバコを吸っても法律に触れんし、少女売春にもなりゃせんぞよ」
と、僕も調子を合わせた。
「やだなァ、あたいまだ高校生よォ、オジサン。
カバン中にセーラー服入ってんだからァー。
嘘だと思うんなら、見せたげましょーかァ?」ミミちゃん、ここでまた普通の口調に戻って、「セーラー服好きなんでしょ、友則君は?」
「あのねー!
なんでそこだけマジに言うんだよ、ミミちゃん!
まるで、僕が変態みたいじゃないか」
「あら、じゃ、セーラー服嫌いなの?」
「そりゃあ嫌いじゃないけど、でもねー……」
「ほらね、やっぱ好きじゃない。
世の中には、そんな趣味持った人もいるのよねー」
「へえー、そう、そういう趣味があったの、友則?」などと、伴ちゃんまで意外そうに言った。
「違うってば、そんなんじゃないって! 僕はー……」
「いーのよ、別に隠さなくっても。
友則君みたいな性癖持った人だって、いることはいるのよねー。
人に迷惑かけなきゃ、変態でも何でもいーじゃない」
「違うんだーっ!
わたしは無実だ、事実無根だ、冤罪だっ!
最高裁は何をしてるんだーっ!
これで良いのか日本の司法はーっ!
お奉行様ぁー、お慈悲を、今一度、今一度お裁きをーーっっ!!」
「ええーい、見苦しいーっ!
この期に及んでジタバタするんじゃねェー、背中の桜吹雪が目にへーらねーかっ!」
「へへーっ!」
「……さっきから、二人で何してるの? 学園祭か何かの、出し物の練習?」
と、ポカーンとした顔をした伴ちゃんがボソッと言った。
「友則君がいけないのよー、せっかくあたしが真面目に統計学してたのに、おちょくって、人をワル乗りさせるんだもん」
「わりー、わりー。
けど、ワル乗りさせたのはミミちゃんの方だと思うけどなー」
「でも、ま、これで安心しちゃったよ」と、伴ちゃんはホッとした表情で、「どうやら、ミミちゃん、病気じゃないみたいだし……」
「すると何か?
あたしが真面目にやるとビョーキで、ふざけてやると正常ってわけ?」
「べ、別に、そういうわけじゃあ……」
「あるんだよね、はっきり言って」と、口ごもった伴ちゃんの代わりに僕が続けてやった。
「んまっ!
……でも、半分当たってるだけに、つらい!」
「『半分』かなぁ……?」