
 第9章へ
第9章へ
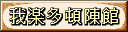
 webmaster@snap-tck.com
Copyleft (C) 2000 SNAP(Sugimoto Norio Art Production)
webmaster@snap-tck.com
Copyleft (C) 2000 SNAP(Sugimoto Norio Art Production)
オヤジさんがソ連軍に連れて行かれてから1ヶ月ほどした頃、
「杉本、ただいま帰りました。 長い間、御心配をおかけしましてすみませんでした」
と挨拶をしながら、またしても唐突にオヤジさんが収容所に戻ってきました。 しかしこの時のオヤジさんは、チフスにかかる前は70kg以上あった体重が病気のために45kgほどに激減していて、しかも顔色が青白くなり、容貌がすっかり変わって別人のようになっていたので、最初は誰もオヤジさんだとはわからず、ポカンとして見返すばかりだったそうです。 でもさすがにお袋さんだけはすぐにオヤジさんだとわかり、オヤジさんのところに近寄るなり、思わず声を上げて泣いてしまいました。
少し落ち着いてから、オヤジさんはお袋さんから自分が書いたという遺書を見せられてびっくりしました。 その遺書の筆跡は確かに自分のものですから、自分で書いたはずなのに、オヤジさんにはそんなものを書いた覚えが全くなかったからです。 おそらく高熱にうかされてほとんど無意識のうちに書いたのだと思われましたが、オヤジさんは自分の亡霊にでも出会ったような気がして、妙に薄気味が悪かったといいます。
こうしてオヤジさんが無事に戻ってきたことにより、お袋さんと兄貴の生活は多少楽になりました。 その頃は秋から冬に入り、いよいよ厳しい真冬を迎ようとしている時期でした。 朝鮮半島の冬は寒さが非常に厳しいため、暖房用具も毛布もろくになく、しかも食べ物も十分にない収容所の生活は非常につらく厳しいものでした。 チフスの流行はようやく下火になっていたものの、その厳しい寒さで餓死者や凍死者が徐々に増える傾向にありましたから、この時期にオヤジさんが戻ってきたのはお袋さんと兄貴にとって幸運だったと言えるでしょう。
オヤジさんが収容所に戻り、使役に出るようになってからも、お袋さんはそれまでどおり残飯漁りに行き、厳しい冬もどうにか越すことができました。 やがて春になり、さらにまた夏がめぐってこようとしている頃から、収容所の中では「何とかして一日でも早く日本へ帰ろう!」という気運が高まり始め、次第にそれが避難民全員の合言葉となっていきます。 このまま収容所にいても、いずれは餓死するか病死するだけだと考えられましたから、どうせ死ぬのなら一歩でも日本に近づいて死にたいと誰もが思っていましたし、収容所を出るとしたら暑さの激しい真夏が来る前が最適だったからです。
そして避難民の代表数名がソ連軍に対して粘り強い陳情を毎日のように繰り返し、とうとう「賑町の日本人収容所にいる避難民が集団脱走したとしても、ソ連軍当局はそれを黙認する」という約束を取り付けました。 ソ連軍側としても、疫病を出したり餓死者を出したりする日本人避難民はやっかいなお荷物になっていましたので、むしろ集団脱走してくれた方が楽だったのでしょう。
こうして1946年(昭和21年)6月上旬のある夜に、賑町の日本人避難民はめいめいわずかなコーリャンと塩とハンゴウ1個を持ち、数十名ごとの班に別れて収容所を集団脱走しました。 オヤジさんは班長でしたので、自分の班の班員ひとりずつに近寄り、氏名と顔を確認してから出発しましたが、その時、誰もがいよいよ出発という感激で涙を流していたそうです。
収容所を出発した避難民は100キロほど南にある北緯38度軍事境界線を目指して、なるべく人家の少ない田舎道を選びながらただひたすら歩き続けました。 集団の中には比較的元気な人もいましたが、杖にすがってよろめくように歩く老人や、子供を連れた女性や病人などもいて、歩くスピードに非常に差がありました。 その上、夜間の行動でしたので班員の掌握がうまくいかず、夜が明ける頃にはどの班も編成がバラバラになり、家族や親しい友人同士など数名のグループを作って行動するようになっていました。
オヤジさんとお袋さんは交代で兄貴を背負い、疲れてくるとお互いに励まし合いながら、できるだけ集団の主流と思われるあたりと歩調を合わせて歩くようにしました。 前を見ても後ろを見ても、目の届く範囲には乞食のような格好をした仲間達がただ黙々と歩き続けていて、たまに比較的元気のある人が「お先に…」と声をかけながら追い越して行きますが、疲れきった様子の老人や子連れの女性を追い越すことの方が多く、主流と思われる集団も徐々にばらけていきます。 最初のうちは、追い越されたり追い越したりするたびにオヤジさんもできるだけ声をかけるようにしていましたが、そのうちに声を出す元気がなくなり、「頑張って下さい、必ず生きて日本に帰るんですよ!」と心の中で励ましながら、小さくうなずきかけるのが精一杯になってしまいました。
半日以上歩き続けた後、先着の人達が道端で炊事をしている所に着きましたので、オヤジさんとお袋さんもそこで枯れ草を集め、食べられる草を取ってきてコーリャンの塩雑炊を作って食べました。 収容所を出てから初めての食事でしたが、手持ちのコーリャンはわずかでしたし、これから何日間ぐらい歩き続けなければならないのかわかりませんでしたので、コーリャンはごくわずかしか使わず、その日の食事はそれだけで済ますことにしました。 食事が済むとゆっくり休む間もなくまた集団と共に歩き出し、そのまま夜まで歩き続けて、やがて潅木の茂った丘の中腹に着きましたので、その日はそこで寝ることにしました。 オヤジさんとお袋さんは木の下に枯れ草を敷いて寝ましたが、二人とも寒さのために一睡もできなかったそうです。
翌日もまた同じような状態で歩き続け、昼頃にコーリャンの塩雑炊を食べ、夜になって今度は山の麓の小さな無人部落に泊まりました。 そこは家畜小屋らしく、家畜の糞の匂いが強くてやはりほとんど眠れなかったといいます。 その次の日は朝から雨が降ったため、全身ずぶ濡れになりながら歩き続けました。 雨のために炊事ができませんので、仕方なく生のままコーリャンをかじり、塩を舐めながら歩き続けました。
この頃には集団が移動するスピードは極度に遅くなっていて、疲労困憊した様子で道端にへたりこんでいる人達が次第に増えていました。 そしてその日の昼頃、さしものオヤジさんとお袋さんもとうとう道端に座り込んで動けなくなってしまいました。 二人ともしばらくの間は放心状態でいましたが、やがてどちらともなく「たとえ一歩でもいいから、日本の土を踏むまではどんなことがあっても死ぬわけにはいかない」と励まし合って、必死の思いで立ち上がり、また這うようにして歩き続けました。 その後も道端に座り込んでしまうことがしばしばありましたが、そのたびにまたお互いに励まし合って、ただひたすら日本に帰りたいという執念だけで歩き続けたのです。
また歩いている途中で、背負っていた兄貴が青黒い顔になり、目を吊り上げて呼吸も脈拍も止まってしまったことがありました。 それを見たオヤジさんが、「可哀想に、竜夫はとうとう死んでしまった…!」と言うと、お袋さんは「たとえ死体になっても、私はこの子を日本に連れて帰ります!」と言って決して放そうとしませんでした。 そうしてしばらく背中で揺られているうちに、兄貴はまた息を吹き返し弱々しくうめき出したのです。 その後も兄貴は何度も仮死状態になりましたが、よほど生命力が強かったのか、それともお袋さんの執念が乗り移ったのか、そのたびにかろうじて仮死状態から蘇生することができました。
こうしてある時は山を越え、ある時は川を渡り、またある時は腰までつかる泥沼地帯を抜けて、死に物狂いの逃避行を数日続けた後、大勢の仲間が一列縦隊になってゆっくりと歩いている地点に着きました。 オヤジさんとお袋さんは何となく不思議に思いながらも、本能的にその列に加わりました。 しばらく歩いて行くと右手の台地の上に軍隊のキャンプがあり、その前に数十名のソ連兵がいてこちらを見下ろしているのに気付きました。 そしてさらに少し行くと、道の両側に自動小銃を構えたソ連兵が並んでいて、みんなをじっと監視しています。 オヤジさんはここまで来てまた逮捕されるのか、それともこの場で射殺されるのかと無気味に思いながら、なるべく彼等の顔を見ないようにして黙々と歩き続けました。
お袋さんは長春の町でいきなり空襲を受けた時の恐怖と、宣川の収容所で自決用の手榴弾を渡された時の恐怖と、このソ連兵が自動小銃を構えている前を膝が震えるのを抑えながら歩いた時の恐怖は今でもはっきり覚えていて、これからも決して忘れられそうもないといいます。
不思議なことにそこを何事もなく通過すると、今度は汽車の踏み切りの遮断機のような柵があって、そこには拳銃を持った数名のソ連の憲兵が立っていました。 その憲兵達が無言で遮断機の柵を上げている前を通り抜けると、雑草の茂った野原の中に細い一本の道が長く続いていて、そこにはソ連軍のキャンプも建物もなくソ連兵も見当たりません。 その一本道を相変わらず一列縦隊になって黙々と歩き続けると、やがて野原の中に小さな部落が見えてきて、そこに仲間達が大勢で休んでいました。 その部落にたどり着いてから、オヤジさん達は今しがた通り抜けてきた遮断機が待望の38度線で、ここは南朝鮮であることにやっと気がついたのです。
それに気がついたとたん、オヤジさんとお袋さんは思わず顔を見合わせヘタヘタとその場に座り込んでしまいました。 二人とも涙と雨と疲労と安心感とで、泣いているのか笑っているのかわからない、何とも奇妙な顔だったそうです。
後になって地図で確認したところ、オヤジさん達が歩いた道はまずピョンヤン(平壌)の収容所からまっすぐ南下して、サリウォン(沙里院)という町を通り、そこから南東に向かってミュラク(滅悪)山脈を越え、さらにそこからまた南下し、38度線を越えてケソン(開城、現在は北朝鮮領)の町に到着したことがわかりました。 途中には小高い山や丘がいくつもあり、河川も数本ある上にケソンの前にはかなり広い泥沼地帯があります。 この100キロ以上におよぶ逃避行は、オヤジさん達が長春を脱出してから日本に引き揚げるまでの間で最後の、そして最大の難関でした。 賑町の収容所を脱走した時は二千人ほどの大集団だったのが、途中で数名ごとのグループに分かれて長く延びた難民の流れとなり、おそらく主流と思われる集団の末尾あたりにいたオヤジさん達がケソンの部落にたどり着いた時には、周囲に千人弱の仲間しかいませんでした。
この逃避行でどれほどの仲間が脱落したのかはっきりとはわかりませんでしたが、生きて南朝鮮までたどり着いた幼児が兄貴ただひとりだったことはある程度確かなようでした。 賑町の収容所に収容された時には兄貴を含めて十数名の幼児がいましたが、栄養失調と病気で次々と死んでいき、収容所を脱走する時にはわずか数名になっていて、そのうち南朝鮮までたどり着いたのは、結局、うちの兄貴だけだったのです。
その頃、北朝鮮各地の収容所の日本人避難民から同じような訴えがたくさん出されていましたので、ソ連の中枢は日本人避難民の解放を決意し、賑町の避難民の集団脱走と相前後して、ついに日本人解放令を発令することになります。