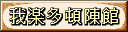
 webmaster@snap-tck.com
Copyleft (C) 2000 SNAP(Sugimoto Norio Art Production)
webmaster@snap-tck.com
Copyleft (C) 2000 SNAP(Sugimoto Norio Art Production)
2020年2月に発足し、7月に自ら解散を申し出て廃止されるまでの約5ヶ月間、未知の新型ウイルスに対して様々な指針を示した「コロナ対策専門家会議」。 その波乱万丈の活動を専門家、政治家、官僚等、多くの関係者の証言で描く、迫真のノンフィクションです!(^o^)/
筆者は、自らの存在や考えを文中に出すことなく、冷静かつ客観的な筆致で、関係者の証言を淡々と記述しています。 しかし、それにもかかわらず――あるいは、だからこそ――、感染を押さえ込み、患者を助けるために、自らの命を削ってまで懸命に奮闘する専門家の使命感と、都合の良い時だけ専門家の言葉を引き合いに出し、政策失敗の責任を専門家に転嫁しようとする政治家の醜悪さ、そして政府および役人の無謬性にこだわって、間違いを決して認めず、反省しようとしない官僚の非人間性と傲慢さが、見事に浮き彫りになっていて、無性に感情を揺さぶられます。
新型コロナウイルスに関心のある人だけでなく、専門知のあり方に関心のある人や、政治と科学と市民の関係に関心のある全ての人に、是非とも読んでいただきたい渾身の力作です。
1970年代のアメリカでパンフレットとして出版され、フェミニズムの古典になった「魔女・産婆・看護婦」と「女のやまい」を収めた初版に、その後の社会変化を解説した序文を加え、訳文も全面的に改めた増補改訂版です!(^o^)/
洋の東西を問わず、太古から医療は女性の役目であり、女性の生得権であり、女性の世襲財産の一部でした。 ところが西欧では、中世に男性権力者(王侯とキリスト教会)がそれを奪い取りました。 そして男性中心の社会構造を作るために組織的に行ったものが魔女狩りであり、火炙りにされた魔女の大半は女性医療家――主に産婆でした。
また女性医療者は主に農民階級の人達を治療していて、王侯や教会に反発する農民階級の人達の自治&反乱組織と深い関係がありました。 つまり魔女狩りは、支配者階級にとって脅威であるそれらの組織活動を潰すためのテロ活動でもあったのです。
本来、医療行為には女性の方が適していて、男性ではうまく処理できない事が多々あります。 そこで診断・治療・看護という医療行為のうち、男性医師は診断と治療(または治療方針の立案)だけを行い、治療の補助と、最も手間がかかる看護は、奉仕を自らの使命と考え、忍耐強く、どんな大変な汚れ仕事でも喜んで行う滅私奉公型の医療労働者――看護婦に押し付けました。 そして医療行為の手柄と報酬は男性医師が独り占めし、看護婦は手柄と報酬を主張する権利もなく、召使いとほとんど変わらない待遇になったのです。
若かりし頃、仕事の都合で医療分野に首を突っ込むようになって、一番驚いたのは、大学医学部の教授を頂点にして医師・看護師・薬剤師・コメディカル等によって形成された専制君主型ヒエラルヒー社会の時代錯誤的な封建性でした (そのヒエラルヒー社会の床下――決して「縁の下(の力持ち)」ではない!――でゴーレムのように蠢いていたのが、製薬業界の人達でした(;_;))。 本書を読んで、そんな専制君主型ヒエラルヒー社会が形成された歴史的背景がよくわかりました。
筆者達は本書の最後を次のような趣旨の文章で結んでいます。
「女性を抑圧しているのは生物学的な要素ではなく、性と階級に基づく社会制度だという事実を理解することが重要である。 そしてその理解に基づいて、社会的な選択肢を女性が管理する権利、現在そうした選択肢を決定している社会制度を管理する権利を求めて行動することが大切である」
フェミニズムや医療分野における性差別の歴史に興味のある人に、本書を強くお薦めします!v(^_-)
帯のアオリ文句にあるように、”8割おじさん”こと西浦博先生が「科学者の社会的使命とは何か?」と自らに問いながら走り抜いた半年間の貴重な記録であり、責任を科学者に転嫁して保身に走る政治家達と、何事も事無かれ主義の官僚達と果敢に切り結び、世間の矢面に立って自ら火中の栗を拾い続ける科学者達の貴重な記録でもあります。 世間からどんなに罵られようと、医学研究者としての使命感に突き動かされて行動する科学者達の、腹の据わった覚悟にムチャクチャ感動してしまいました。
製薬企業の新薬開発プロジェクトや、厚労省の班研究や、AMED(日本医療研究開発機構)の統合プロジェクト等にデータ解析屋として関わった僕は、(これほど過酷ではありませんが(^^;))西浦先生と似たような仕事を経験しました。
データ解析屋は裏方ですから、表に出ることはめったにありません。 ところが図らずも表舞台に引っ張り出されてしまった西浦先生は、それならばと、従来の父権主義的――paternalism、強い立場にある者が、弱い立場にある者の利益のためだとして、本人の意志は問わずに介入・干渉・支援すること――な政策決定ではなく、意思決定支援――risk informed decision、対策として考えられる全ての選択肢について、そのベネフィットとリスクの情報を全て公開した上で、政府または国民が主体的に意思決定するのを支援すること――による政策決定に挑戦しました。 その結果、脅迫状が届いたり、殺害予告を受けたりしながらも、果敢に挑戦し続け、現在も最良の方法を模索し続けられています。
COVID-19と科学コミュニケーションに関心がある、全ての人に読んでいただきたい本です。(^o^)/
ベトナム帰還兵が「ほんとうの戦争は無慈悲で残虐で愚かで、そして無意味です」と語り、殺し合うことの悲惨さと命の尊さを訴えた2冊の名著です。 前著は講談社「シリーズ・子供達の未来のために」の中の一冊であり、子供向けなのに対して、後著は大人向けの続編といった感じです。
著者のアフリカ系アメリカ人であるアレン・ネルソン氏は、貧困と人種差別から抜け出すために18歳で海兵隊に志願し、19歳でベトナム戦争の最前線で戦います。 そして除隊後、戦争によるPTSD(心的外傷後ストレス障害)に長い間苦しみ、それを克服する過程で非暴力に目覚め、日米両国で精力的に平和活動を行いました。
後著の中でネルソン氏が、
「私には、日本の国全体がPTSDにかかっていて、侵略の記憶を政治家や大人が語れず、学校でも教科書でも、教えないような状態にあるように思えます。 私の経験から言うと、そういう状態ではいつまでたってもPTSDを克服することはできないと思います」
ネルソン氏が語る「ほんとうの戦争」は、軍人家系に生まれて軍人になり、第2次世界大戦の敗戦後は満州難民になった親父さんが、折りに触れて話してくれた内容と大変よく似ています。 ネルソン氏と同様に、親父さんがPTSDを克服するために自分が行った非道な行為を目をそらさずに見つめ、「ほんとうの戦争」について語ってくれたのかどうかはわかりません。 でも息子としては、親父さんが「ほんとうの戦争」について語ってくれたことに感謝しています。
「映画カンタ!ティモール上映会・広田奈津子監督×しばやん講演会」で購入した、東ティモール本です。 著者の南風島渉氏は報道写真記者であり、「カンタ!ティモール」にも登場します。
本書を読むと「カンタ!ティモール」の背景がよくわかり、東ティモール問題をより多面的かつ立体的に把握することができると思います。 そして東ティモール問題に対する日本政府の悪辣な非道ぶりと、欧米諸国に根強く残る植民地主義についても知ることができ、「政府とマスコミの言うことを信用してはいけない」という当たり前のことをあらためて実感することができます。
そして何よりも、こういった問題に無関心でいるのは、虐殺や弾圧やレイプといった非人道的な行為に間接的に手を貸すのに他ならないということを、はっきりと自覚させてくれます。 本書を映画「カンタ!ティモール」とセットでお薦めします。v(^_-)