・「青空どろぼう」阿武野勝彦監督、2011年、日本
「平成ジレンマ」で一部のコアな映画ファンに強烈な印象を与えた、阿武野勝彦監督の最新ドキュメンタリー映画です。戸塚ヨットスクールの現在を圧倒的な迫力で描いた「平成ジレンマ」と違い、四日市喘息という公害の歴史を淡々と描写することによって、観客に深くて重い思考を促す作品になっています。
この作品は福島の原発事故の前に完成していましたが、期せずして、福島の原発事故について深く考えさせられる内容になっています。これは、責任の所在を曖昧にするために「公害」という言葉を作り出した経済最優先の社会構造が、昔も今も全く変わっていないからであり、大都市の経済的繁栄が、その周辺の町の住民の犠牲の上にアグラをかいたものであることを再認識させられます。
この作品の主人公の一人である澤井余志郎氏は、四日市喘息の患者達を支援する活動を40年にわたって無償で続けてきた人であり、「何よりも事実は強い」という信念に基づいて、事実を記録してそれを人に伝えるという活動を現在も継続している”公害記録人”です。この人の信念と活動内容、そしてその成果を見ていると、ジャーナリズムとマス・メディアあるいはマスコミは全く別物だということがよくわかります。
またもう一人の主人公である野田之一氏は公害裁判の原告の一人であり、38年前、公害裁判で勝訴した時に、支援者に対して「まだ、ありがとうとは言えない。この町に本当の青空が戻った時、お礼を言います」という強烈なメッセージを残した、元漁師の喘息患者です。この人は公害裁判を企業対患者、権力対個人というステレオタイプな対立構図に落とし込まず、次のようにもっと大きなものとして捉えています。
「日本が敗戦の混乱から高度経済成長に向けて突っ走り、強引に近道をしようとしたために無理が生じた。その無理が産み出したものが公害なのだ。コンビナートで働く人達も、みんな日本のために良かれと思って必死に働いてきたのだから、コンビナートやそこで働く人達を憎いと思ったことはない。
ただ無理が何をもたらすかを知ってもらい、一度立ち止まって、それについてみんなで考えてもらうために我々は公害裁判を起こした。
コンビナートで働く人達がワルモノで、我々患者がイイモノというわけでは決してないのだ。
「エコロジー」や「ボランティア」という外来語よりも、「もったいない」や「お互い様、おかげ様」という日本語の方がしっくりくるのと同様に、「デモクラシー」や「市民活動」という外国の概念よりも、このように「お互い様」という考えに基づいた懐の広い活動こそが日本の市民活動のあるべき姿だと思います。
この野太くておおらかなヒューマニズムに対して、企業の経営者や政府は、「コンビナートを止めると日本経済が大打撃を受け、日本が潰れてしまう。日本の繁栄のためには多少の犠牲はやむを得ない」という、昔も今も変わらない欺瞞に満ちた言い訳で対応しました。
第2次世界大戦前、政府と軍部は「満州は日本の生命線であり、これを手に入れないと日本が潰れてしまう」と主張して中国に侵略しました。そしてその結果、日本は戦争に敗れましたが、政府と軍部が主張したように日本が潰れることはなく、むしろ第2次世界大戦前よりも繁栄しています。これは、独裁政治をやめて民衆の権利を認め、戦争を放棄して平和に暮らし、財閥による富の独占をやめて民衆に富を公平に分配すれば、国全体が繁栄するという見事な実例です。
公害についても、企業が公害対策に費用をかけたために企業が潰れ、日本が潰れるということはなく、環境が改善して労働条件も向上したため、長い目で見ればむしろ企業の業績は向上し、当時に比べて暮らしやすく豊かな社会になっています。
こういった歴史を振り返ると、政府や企業の経営者が「日本のため」と言いながら、その実、自分達の目先の利益しか考えておらず、いかに近視眼的かつ利己的かということがよくわかります。
誰もが原発問題について否応なく考えざるを得ない今、この映画を多くの人に観てもらいたいと思います。












 管理室へ
管理室へ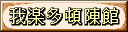
 webmaster@snap-tck.com
webmaster@snap-tck.com